19社会学


社会学は「集団の一員としての人間」という観点から、個人を取り巻くあらゆる社会関係や、その中での人間の営みを探究し、人間の行為とその意味を客観的に分析します。家族や学校、企業、地域社会の問題から、都市、産業、メディア、文化、国際社会、人類のテーマまで多彩であり、「人間の集団と関わりのある事象」はすべて社会学の研究対象となります。
また具体的な研究対象は幅広く、「格差問題」「非正規雇用」「命の尊厳」「ジェンダー」「テロリズム」「SNS」「過疎化」「まちづくり」など、社会に起こっている現象や問題を取り上げて分析し、提言や注意喚起を行っていきます。社会学では、研究する目的の場所に出かけて、情報収集のためのアンケートやインタビューなどの聞き取り調査を行う「フィールドワーク」を重視するという特徴があります。
学んだことを実践できる就職先はバラエティに富んでいます。製造業や流通・サービス業で商品開発や販売戦略を手がける人、情報収集が欠かせないマスコミ関連やマーケティング関係で活躍する人、公務員として公共の問題の解決に携わる人もいます。
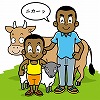
弘前大学 人文社会科学部 教授 曽我 亨 先生
「人の振りみて我が振りなおせ」という格言があります。他人の嫌な言動や態度をみたら、それを自分に置きかえて省みようという意味ですが、人類学もこれに似た考え方をします。自分の振る舞いを、客観視することはとても難しく、だからこそ異文化に生きる人々と一緒に暮らし、驚きや違和感を手がかりに、私たち自身のことを知ろうとするのです。また逆に、私たち自身のことを手がかりに、彼らの振る舞いを理解しようともします。哲学が本を片手に考えをめぐらせるのとは対照的に、人類学はフィールドに出かけて、身体で体験しながら人間について考える学問です。
あなたは自信に満ちて生活していますか? 北ケニアの牧畜民と暮らすと、彼らがとても自信に満ちていることがわかります。一方で学生に「自分はダメだと思ったことがあるか?」と聞くと、ほとんどの学生が手を挙げます。ということは、この感覚はあなただけが感じる個人的な現象ではないということです。むしろ日本の社会こそが、あなたにそう思わせているのだと考えられます。牧畜民と私たちの社会を比べることで、自己肯定的な生き方を実現するヒントがみえてきます。
牧畜民たちは、どうして自己肯定的な生き方ができるのでしょうか。フィールドワークによって、彼らは家畜とともに生きており、「子どものうちは羊の放牧を、青年になると牛の放牧をする」というように、自分の未来を予測できる社会に生きていることがわかります。一方、私たちが暮らす現代の社会は、「未来を現在よりもよくするために、人は変わり続けなければならない」という価値観をもとに作られており、人は常に「このままではダメだ」と変化を求められます。
近年、私たちの社会も大きく変わり、未来の不確実性も高まってきました。不確実な社会を生きるにはどうしたらよいでしょうか。地域の人たちの考えを拾いあげ、充実した「今」を生きる術を考えることも、人類学の大切な役割です。

東京大学 教養学部 教授 和田 毅 先生
学生や市民が人を集めて、社会への不満やその改善を訴える行動を「抗議行動」と言います。抗議行動には穏やかなものから暴力的なものまでさまざまなものがあります。また、抗議行動の主体も多様ですし、抗議の対象も学校や企業、政府といろいろです。
社会学で抗議行動を分析するのに、新聞などから抗議行動の記事を集め、「いつ、どこで、誰が、誰に、どのような手段で、なぜ」という項目で分類し分析する方法があります。これを「イベント分析」と言います。
この手法で、18世紀後半から19世紀初頭まで、つまり産業革命期のイギリスでの抗議行動のデータを見ると、興味深いことがわかります。
まず18世紀には、一般民衆が地元の商人や土地を所有する貴族、そして地元政府の役人などに対して、石を投げたり火をつけたり家の窓を割ったりといった、暴力的な抗議が多数を占めています。しかし、19世紀になると、公開集会や嘆願活動のような暴力を用いない穏健な形の抗議行動が主流になってきました。なぜ、このような変化が起きたのでしょうか。
これには、イギリスの政治体制の大きな変化が関連しています。権力が国王や貴族から議会へ、地元の政府や領主から中央に移動していったのです。これに対応して、民衆の抗議行動も暴力的なものから議会に対して訴える形に変化していきました。
食料など生活必需品を握っている商人や地元の役人などが抗議の対象なら直接その対象相手に暴動をおこす手段が有効なこともありましたが、議会が力を持ってくると、ものごとを変えるにはロンドンにある議会に圧力をかけなくてはならないと国民が理解し始めました。それにより、嘆願や集会といった形の抗議行動が増えていったのです。
このように新聞記事という質的データを数値化するイベント分析を用いることで初めて見えてくることはたくさんあります。現在は、こうした過去のデータだけでなく、リアルタイムの抗議行動をデータ化するための研究も進んでいます。

宮崎大学 地域資源創成学部 地域資源創成学科 教授 熊野 稔 先生
少子高齢化と人口減少が、社会問題になっています。仕事や暮らしの舞台である「まち」を持続させるためには、さまざまな「地域資源」を総合的に検討し、持続的な発展を実現できるまちづくりや村おこしの取り組みが必要です。そのためには、十分な「実現可能性調査(FS:Feasibility Study)」を行い、公共事業としての投資効果が得られるかどうかを見極める必要があります。そうした手法について研究するのが、「地域経営学」「都市計画」などの学問分野です。
1991年から社会実験が始められ、1993年に全国に103カ所が開設された「道の駅」は、人気の高まりにともない、2017年4月時点で1117カ所に増えています。円滑な交通を支える休憩場所としての機能、情報発信機能、地域連携機能を併せ持つ、「地域とともにつくる個性豊かなにぎわいの場」としてスタートした道の駅は、近年は、24時間利用可能なトイレや駐車場を備えた公共施設として、災害時の避難場所や食料支援など、「防災機能」も発揮しています。
全国で最初に社会実験が開始された、「道の駅ゆとりパークたまがわ」(山口県萩市)の場合、地域の人々から「道の駅ができていなかったら、まちは存続しなかったかも」と、評価されています。田万川エリアは、県内屈指の果物生産地ですが、道の駅のおかげで販売量が伸びたほか、売れ残った果物は、ジュースなど加工品として販売できるようになりました。当然、雇用拡大にもつながっています。
高齢化地域における「買い物難民」対策として、各地の道の駅には今後、食料品や日用品の宅配を行う機能なども期待されています。それを実現させるには、地元企業の「CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)」とのコラボなど、新たな手法を検討しなければならないでしょう。
料金(送料含) : 350円
発送予定日: 明日発送発送日の3〜5日後にお届け
地域政策に興味があり、実践的な教育を行っているため。
地方自治に関する専門知識や政策立案能力、多数の学問を学べること。
料金(送料含) : 350円
発送予定日: 明日発送発送日の3〜5日後にお届け
学習環境、とくに図書館が充実しており、利用したいからです。
興味のある分野に教わりたい教授がいるから。
情報教諭の免許が取得できるため。また、司書、学芸員の資格も取得できるため。
自分が将来就きたいと思っている仕事に近づける教育プログラムがふくまれていたため。
地域資源創成学部では街の成り立ちや文化を研修や講義によって学ぶことができるため選びました。
自分がやりたかった地域活性化について力を入れておられたので、そこで学びたいという気持ちが強かったから
料金(送料含)
:
 400円
400円
発送予定日: 明日発送発送日の3〜5日後にお届け
弘前大学 人文社会科学部
社会学系の分野を網羅できること
弘前大学は総合大学で様々な学部の人達と交流できることが魅力的だと感じました。