50獣医学
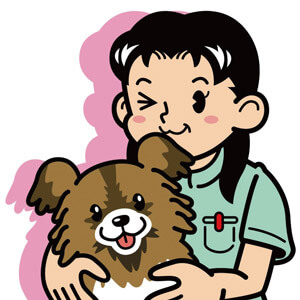
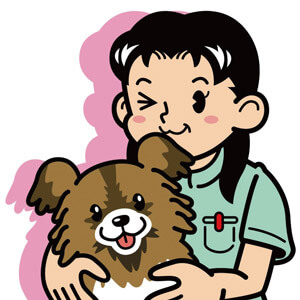
獣医学は、6年制のカリキュラムを基本として、産業用動物やペットの病気の診断や予防、治療を行う獣医師の養成を主目的とする学問です。BSE(牛海綿状脳症)、鳥インフルエンザなど家畜の伝染病の発生は深刻な問題で、その予防など病気への対応は、獣医師の重要な職務です。また、4年間のカリキュラムで愛玩動物看護師や認定動物看護師、介助犬の養成などをめざす獣医保健看護学を学べる学科もあります。
獣医師が活躍するフィールドは、動物の診察や治療だけにはとどまりません。獣医師の職域としては、食品の衛生検査・監督・指導、動物用・人体用の医薬品の開発研究、野生動物の生態調査やその保護、バイオテクノロジー分野の研究など、一般的な獣医師のイメージではとらえきれない活躍の場があります。
獣医師などの専門職に就く人が大半です。官公庁の公衆衛生や畜産部門、農業団体、競馬関連公的機関への就職も人気があります。民間企業では、畜産、乳業、飼料、食品メーカーでのスペシャリストとしての活躍が期待されています。

ヤマザキ動物看護大学 動物看護学部 動物看護学科 教授 今村 伸一郎 先生
骨は私たちにいろいろなことを語りかけてくれます。ある動物の骨を見て、さらにほかの動物と比較をして、初めてわかってくることもあります。例えば、足の先の骨を見ると、動物は人間と違い、かかとをつけず、つま先で立っていることがわかります。つま先で立つと足の親指が地面から浮きます。犬の骨を見ると後足の親指の骨はほぼ退化していますが、犬の祖先にあたるオオカミにはまだ親指があります。それは、オオカミが岩場を走るときに親指を使うためだと考えられています。逆に犬は親指を使わないので退化したのです。このような進化の過程は骨を見て、ほかの動物と比べることでわかるものなのです。
動物の足の指の数を比べると、興味深いことがわかります。つま先立ちの4本から3本、2本、1本とさらに少ない動物がいるのです。例えば馬は1本です。実は地面につく部分が少ないほど速く走れるのは力学的に証明されています。馬の足の指は速く走るために1本だけ使われるようになったのです。
ところで、猫やチーターといったネコ科の動物も走るのは速いですが、足の指は4本あります。これには別の骨の構造が関係しています。ネコ科の動物の背骨は一つひとつがとても柔らかく隙間があります。骨同士の間に隙間があると動きが滑らかになります。猫が走るときに、背中を丸めているのを見たことがあるでしょう。それは背骨の隙間を縮めて全身をバネにしてスピードを出しているのです。これも骨格からわかることなのです。
このように、動物の骨は私たちに多くのことを教えてくれますが、それは、具体的には何の役に立つのでしょうか?
例えば、骨格の成り立ち、構造の意味を理解することで、できるだけ動物に負担を掛けない看護を行うことが可能となります。動物看護の現場では、骨からのさまざまなメッセージを理解することが求められるのです。
料金(送料含) : 215円
発送予定日: 明日発送発送日の3〜5日後にお届け
動物学を全般的に学びたかったから
動物行動学の研究室をもつ先生がいらっしゃったから。
モデル犬制度があり、高齢動物看護学があるから
動物と向き合う仕事に適した授業内容であるため。
野生動物について学べるから
大学の環境は学びや研究がしやすい場所となっており、自分が動物の遺伝子の研究をするのに最適だと思った。
獣医師になるために、獣医学部のある学校。愛玩動物よりも大動物に強い大学。
獣医師免許取得、鳥インフルエンザ研究実績
北海道大学 獣医学部
海外協力など、国際的なレベルの教育が受けられる。野性動物学研究室がある。
動物実験施設(AAALAC完全認証取得)がある