33航空・宇宙工学


航空機やロケットの開発、宇宙ステーション計画、人工衛星の利用などに必要な先端科学技術を生み出す、スケールの大きな学問です。小惑星探査機「はやぶさ」の帰還や、日本人宇宙飛行士の宇宙ステーションでの活躍などに見られるように、宇宙の謎を解明し、人類の宇宙への進出を実現することをめざしています。
空気の流れや抵抗などの問題を研究する「流体力学」、機体の設計やその材料などについて研究する「構造力学」、航空機やロケットのエンジンなどの開発を行う「推進工学」、機体の姿勢や軌道制御などのシステムについて研究する「制御工学」の4分野があります。航空機は安全性はもちろんですが、環境に配慮した燃料効率などが課題となっています。未知の領域も多く、常に新たな課題に取り組める学問分野です。
航空機メーカーや航空会社、電機メーカーの宇宙・ロボット部門、精密機器メーカー、鉄道関連企業などへ就職する人や、航空機整備、パイロットの資格取得を見据えて就職する人が大半です。航空・宇宙関連の研究所、関連官公庁などで働く人もいます。

東京大学 工学部 航空宇宙工学科 教授 土屋 武司 先生
マッハ5で飛行する極超(ごくちょう)音速機を開発し、東京とアメリカ西海岸とを片道約2時間半で行き来できるようにする、そんな夢のような研究が進んでいます。その実現には、マッハ5に達する超強力なエンジンの開発、従来の航空機とは比べ物にならない激しい騒音への対策、空気の大きな抵抗や圧縮による高温への対策などが必要です。いわば極限状態で飛行可能な航空機を、設計や制御の最適化の研究によって開発しようというものです。
極超音速機の研究では、各要素で技術開発を行ったのち、それらを統合したシステム全体がどのように作用するか、実験データを積み重ねる必要があります。そのためには飛行試験を行わなければなりません。その方法の一つとして、既存の観測用ロケットの先端に搭載した小型実験機を大気圏外で分離し、大気圏に再突入させることでマッハ5程度の試験環境をつくることが検討されています。既存の観測用ロケット打ち上げシステムを利用するので準備期間が短くてすみ、コスト的にもメリットがありますが、試験環境がわずか数秒しか持続しないのが課題です。そのため、機体を水平姿勢近くまで引き起こし、より長い時間、試験環境が持続できないか検討が進められています。
観測用ロケットによる飛行実験で成果が得られれば、極超音速で巡航できる実験機、さらに離着陸可能な無人機、そして極超音速の旅客機を順次開発する計画です。極超音速旅客機が開発されれば、次は宇宙まで行って帰ってくる「スペースプレーン」の実用化も現実味を帯びてきます。スペースプレーンはロケットのように使い捨てずにそのままで繰り返し使うことを前提としているため低コストで、「宇宙観光」や「宇宙輸送」の実現に近づきます。
スペースプレーンの構想自体はかなり以前から研究が進められていますが、いまだ実現にはいたっていません。極超音速機の研究から夢のスペースプレーンが実現するのか、期待が高まります。
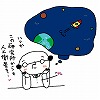
帝京大学 理工学部 総合理工学科機械・航空宇宙コース 准教授 河村 政昭 先生
地球の周回軌道上には、多数の人工衛星が存在しています。通信やネットワーク形成、地球の観測、宇宙観測、最近計画されているものではデブリ(宇宙ゴミ)の回収など、人工衛星の担うミッションには、さまざまなものがあります。新しい人工衛星を設計する際には、それが宇宙でどのようなミッションを行うのかをふまえ、その目的に応じた大きさや構造、発電機器、部品などを選ぶ必要があります。
地上から高度約400キロ~36,000キロ上空にまで打ち上げられる人工衛星には、真空環境、極端な低温環境、時に太陽にさらされ続ける際の高温環境など、過酷な環境に耐えながら正常に動作できるような設計が求められます。設計段階でのコンピュータ上でのシミュレーションや、「スペースチャンバー」と呼ばれる実験装置を用いた熱環境試験(真空環境・熱環境を模擬)は不可欠です。電磁石と地球の磁場を利用して姿勢制御を行う「磁気トルカ」の設計や、通信環境を確保するためのアンテナの設計、発電に必要な太陽光パネルの設計、太陽風が起きた際の宇宙放射線にも耐えられる基板の工夫など、考慮しなければならない要素は数多くあります。
また、地球の周回軌道からさらに外、火星など別の惑星に向かう惑星探査機には、さらに過酷な環境にも耐えうる設計が求められます。宇宙空間では、人工衛星の部品が壊れても修理することは不可能なので、使用する部品はある程度ローテクなものでも、より信頼性の高いものが選ばれることが多々あります。
最近では、大学や研究機関などが設計する小型で低コストな人工衛星が注目を集めています。こうした小型の人工衛星は、ほかの人工衛星や探査機とロケットを相乗りするなどして打ち上げられ、それぞれが目的とするミッションを果たしています。あなたの設計する人工衛星が、いつの日か、周回軌道上で地球を見守る日が来るかもしれません。

横浜国立大学 理工学部 機械・材料・海洋系学科 教授 北村 圭一 先生
飛行機は空気の力を利用して空を飛びます。飛行機がエンジンの力で加速すると、その形状から翼の上と下を流れる空気の速さに差が生まれます。その結果、翼の下が高圧、上が低圧になって下から上に押す力がはたらくのです。これが揚力です。ヘリコプターでも原理は同じで、回転している羽根の上と下で圧力差が生まれて、上に持ち上がるという仕組みです。ロケットの場合は翼の揚力は使いませんが、羽根をつけ、空気の流れを調整し、思わぬ方向に行かないようにしています。
飛行機やロケットのように固定された翼を持つものを固定翼機、ヘリコプターのような回転する翼を持つものを回転翼機といいます。回転翼機の場合、一方向に回転することから、進行方向の右側と左側で揚力が不均衡になります。回転翼のドローンが当初すぐに落ちてしまったのは、これが関係しています。もちろんモータなどの問題もありますが、ドローンの改良にも「空気力学」が貢献しています。
地上を走り、空を飛ぶこともできる「空飛ぶ車」が構想されています。いろいろな用途が考えられますが、まずは災害や事故の際の人命救助での活用が期待されています。ドローンは災害が起きたときにものを運ぶことに使われますが、人を運ぶにはドローンでは力が足りません。
空飛ぶ車も固定翼型と回転翼型が考えられますが、固定翼型は滑走路が必要なので、滑走路なしで飛べる回転翼型の方が有望です。既存のヘリコプターだとヘリポートが必要ですし、着陸できる場所が限られますが、車に近いものであれば、いろいろな場所で活躍できます。着陸した後も、車として移動できるので、可能性が広がります。今は安全管理の面などでいろいろと議論が分かれていますが、技術ができ、多くの人が使うようになると、ルールも整備されてくるでしょう。

高知工科大学 システム工学群 航空宇宙工学専攻 教授 野﨑 理 先生
ジェット機は世界中を飛ぶ最速の移動手段です。その機体やエンジンの製造は、複数の国が参加して行われます。1980年代、英米独伊に日本も加わった5カ国による国際共同開発で、「V2500」というガスタービン方式のジェットエンジンが開発されました。これは、エアバス社のA320など中規模サイズの航空機向けに大ヒットし、日本はこの共同開発に参加して大きな自信をつけました。
第二次世界大戦中、日本は高い航空技術を有し、終戦直前に「橘花(きっか)」というジェット機を完成させていました。しかし日本では敗戦後の7年間、戦力につながる航空産業そのものが禁止されました。そのため、当時の優秀な航空関係の研究者や技術者たちは鉄道や自動車などの分野に移り、やがて日本の高度経済成長を支えていったのです。
この空白の7年の間に、欧米の航空産業が世界の市場を占有しました。日本のメーカーは再スタートを切ってから、ボーイング社などのライセンス生産などを続けることで生産技術を高めるとともに、国の研究開発プロジェクトなどで航空機やジェットエンジンの設計開発技術を着実に高めてきました。
国産のジェット旅客機開発は、日本にとって国家プロジェクトでもあります。国の長期的な働きかけもあり、海外との共同開発や日本が分担する製造割合を高めてきた結果、海外大手と競合しない小型クラスですが、三菱重工業が国産のジェット旅客機を開発し量産を開始することで日本がジェット旅客機の市場に参入する時代になりました。
現在のガスタービン方式に代わる次世代航空機として、電動化も研究されており、世界中が電動航空機開発にしのぎを削る時代へ入ってきました。超音速エンジンのように速さを競う研究もありますが、地球環境に配慮した持続可能な推進技術の開発は世界的な課題です。
航空宇宙工学を学びたかったから
施設や学習環境が整っていることからこの大学に決めました
航空宇宙工学と船舶海洋工学が同時に学べる唯一の大学だから。
物理に大変興味が有る反面、文系知識も身に付けたいと考え、機械工学に強い総合大学として横国大を選択しました
実験施設が整っているのと航空宇宙工学が学べるから。
この大学では、必修科目がなく全ての科目を自分で選択するので、自分の学びたいものだけを学べます。
衛星を打ち上げてみたい
宇宙工学の研究に力を入れているから。
東京大学 理科一類
航空宇宙学が盛んで、専攻したいから。
宇宙物理を学ぶのに最高の環境が整っているから。