44経営工学
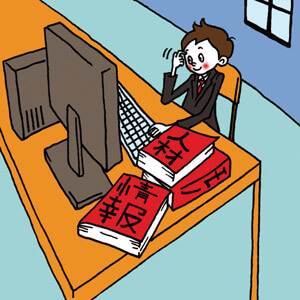
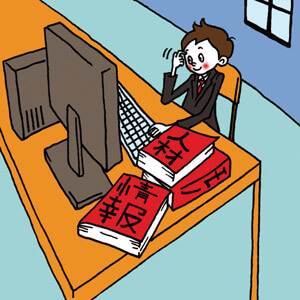
経営工学は、企業経営の効率化を図るために、人材・モノ・金・情報という経営資源をどう使えばいいかを、工学的な手法を使って研究する学問です。企業の組織・生産設備・製造工程・品質管理・流通・販売などのあらゆる側面から研究を行います。現代の企業経営は経営に関する専門知識だけではなく、コンピュータを活用した情報分析や生産・販売システムの構築などに関する知識も必要で、その両方を備えた人材が求められています。
研究テーマには、生産や流通における「技術革新」、効率よく質の高い製品を製造するための「生産・品質管理」、経営上の的確な意思決定をするための「情報の活用」に関する研究、企業の経営状態の分析・評価を行う「経営管理」、事故の予防や職場環境の改善のための「人間工学」などがあります。
各種製造業、コンサルタント、シンクタンク、商社、金融・保険業、流通・サービス業など、就職先は多岐にわたります。コンピュータ技術のノウハウにより、システムエンジニアとして迎えられる人もいます。起業家や独立開業をめざす人もいます。

秋田県立大学 システム科学技術学部 経営システム工学科 教授 嶋崎 真仁 先生
2013年10月の会員数が「Tカード」は約4700万人、「Pontaカード」は約5800万人を超えました。都市圏の大企業はポイントカードを使って購買データを収集し、生産管理や在庫管理に反映させています。解析技術の発達により、例えば、どんな商品がよく一緒に購入されるかなどがわかるようになったため、生産効率は確実に上がっています。またこれらの企業は培った経営手法を工学的に体系化し、品質管理や安全管理にも生かしています。一方で、地方に根差した地場企業には、昔ながらの経営をしている企業も少なくありません。
地場企業は厳しい状況に置かれています。人口減少により製品を購入する人が減り、勝負しようにも品質やコスト面で遅れを取ってしまうことが多いからです。資金や機材の不足などさまざまな理由が考えられますが、最も大きいのは情報量でしょう。
品質管理の進歩に功績のあった団体や個人に贈られるデミング賞は、2011年、2012年とインド企業が席巻しています。もはや「高品質」は、日本企業の専売特許ではないのです。インドや東南アジアの製造業が躍進したのは海外に生産拠点を移した大企業がノウハウを注ぎ込んだためで、その結果、地場企業が不利益を受ける形となりました。
画期的な製品を開発するなど、本来は自社だけで状況を打破できればよいのですが、コストやリスクを考えると難しいでしょう。そうなると特に製造業であれば、いかに大企業に部品を供給する立場になれるかが経営の鍵を握っています。基本的には国内の生産を縮小させている企業の方が多いですが、例えばトヨタは売れ筋商品である「アクア」の生産を岩手県で行っており、周辺の地場企業の経営状態も良好です。生産効率や品質を向上させるだけではなく、上向きになっている産業や将来性のある産業を見抜いて食い込んでいくことが、地場企業にとっての勝ち残る方法だと言えるでしょう。

中央大学 国際経営学部 国際経営学科 教授 河合 久 先生
製造業では生産に要したコストを正しく計算する必要があります。しかし、企業によっては生産現場と経理が切り離されていて、正しく計算できていません。例えば生産に携わる社員の給料は、企業から見たら生産コストとなります。しかし正確な生産コストは、製品を作るために社員が働いた生産時間を見なければわかりません。経理が給料の額面でコストを計上すると、正確なコストを反映していないことになります。企業の存在意義である社会性、利潤性、持続性という3つを満たすためには、コストと生産時間の効率化を図ることが重要です。しかし現場を調査すると、うまくいっていない事例が多くあります。
そこで、生産時間を正確に把握するためにIoT(モノのインターネット)を導入する工場もあります。IoTを生産現場で利用すると、生産や流通の工程をタイムリーに測定してデータ化することができるからです。人間が働いている現場では、ロボットとは違い、どうしても生産時間にばらつきが出てしまいます。そのため、作業能率が悪くなると時間単位のコストが高くなり、利益が少なくなります。そうなると、生産現場では作業能率を上げようと考えます。IoTでコストを正確に計測するための生産管理や情報化の方法を考えていくことが、今後の研究に求められています。
また、ニーズを把握して会計に必要な情報を調整する、というアプローチも必要とされています。会計には各国の法律や習慣も関係してくるので、会計に必要な正確な情報を集めるためには、組織文化と会計情報システムの関係に目を向ける必要もあるのです。
例えば海外進出している日本の企業が、海外拠点で日本の会計システムを使うと、各国の法律や習慣に合わなくなってしまいます。そのため、海外拠点ごとに独自の会計ソフトで業績報告書を作成するという方法をとる企業が多く、全体像の把握には拠点間の調整が必要なのです。

東京都立大学 システムデザイン学部 電子情報システム工学科 教授 梶原 康博 先生
工場で製品を作る際、材料や部品に混入している異物を取り除くための目視検査が行われます。しかし人間のすることに絶対はありませんし、例えば原料が小豆のようなものだとサイズや色合いのよく似た小石が混じっているなど、見極めが難しいこともあります。そこで作業のアシストに使われているのがカメラを用いた画像処理技術です。普通の石は通常のカメラ、小豆と似た色合いの石は赤外線カメラと、複数のカメラを使い分けて判別することによって精度を上げることができます。
また出荷の際には、数百と積まれた製品をひとつずつ数えるという単純作業があります。鉄板のように一枚当たりの厚さが正確であれば全体の高さを測ることで枚数も導き出せるのですが、ベニヤ板のようなものだとそうはいきません。ベニヤ板は水分を含むと膨らみ、あるいは下の方は重さで圧縮されるなど、同じ枚数でも厚さが異なるからです。ほかにも熱交換器に使われる大量のパイプの清掃など、工場内には「数える」必要のある作業が意外にたくさんあります。そうした作業もカメラが手助けすることで、スムーズに行えるのです。
一方、部品や完成した製品の運搬も作業者の負担になっています。運搬は主に物流会社の作業員が担っているのですが、20キロ以上もある重い商品を何個も運ばなければならないなど、かなりの重労働もあります。身体への負担を軽減するためねじる動きをなくすなど、作業の動きを変えるのもひとつの手なのですが、作業効率が落ちてしまうケースが多いのです。
そこで、もともとは農作業や介護用に開発された、ゴムバンドの弾性や電動の仕掛け、人工筋肉などを動力に用いた人の動きをアシストするスーツ型の装置が注目されています。しかし付加価値を生まない作業にどれほどのコストをかけられるのかという点からも導入はなかなか進まず、汎用化までにはまだ課題が残されています。

金沢工業大学 情報デザイン学部 経営情報学科 教授 松林 賢司 先生
経営学の最近の流れのひとつとして、「マネジメントサイエンス」と言われる領域があります。工学や情報処理の能力を経営に生かす、いわば「科学的な経営学」です。統計、マーケティングの手法や情報工学の技術、つまり数学や理系の概念を使い、どうやったらものが売れるかなどの経営課題を解決しようという理論です。マネジメントサイエンスの研究は、企業との共同で、その企業の実際の問題点を見いだし、事業開発や商品開発をするという実践的な内容になります。
クラフトビールまたは地ビールと言われる、小規模醸造所が製造・販売するビールの販路拡大を例に、見てみましょう。クラフトビールは、地域活性化を進める地産地消物品として日本各地に広がりつつあります。あるビールは、県の名産品である六条大麦と全国有数の天然水を使って研究開発、製品化され、お土産として高い評価を得ています。
このビールを「お土産もの」から脱却させるための販売戦略とビジネスプランの策定、国内外の販売拡大のプロモーションについての研究が、企業と大学の共同で行われました。
さまざまなデータから、地産地消のクラフトビールは世界的なトレンドであり日本でも今後必ず伸びるという市場分析が行われ、プロジェクトの展開を、(ステップ1)地元に愛される→(ステップ2)都市圏へ供給する→(ステップ3)北米・欧州への展開、と設定しました。マーケティングも、ネットアンケートやグーグルトレンドを使ったネット上の関心ワードの動向把握など情報技術を駆使して行った上で販売戦略を策定し、最終的には本場である北米や欧州など世界でも認知されるブランド価値の創出をめざそうというのです。
科学的な手法を経営学に取り入れることで、みんなが思いつかないような革命的なアイデアを生み出すことができるのではないかと、「マネジメントサイエンス」は期待されているのです。
料金(送料含)
:
 400円
400円
発送予定日: 本日発送発送日の3〜5日後にお届け
情報に興味があるので、施設環境も含めて学習しやすいと思ったから。
少人数教育とカリキュラムが自分のやりたいことにあってる。
国際経営学部の英語で7割の授業が受けられる事、4週間の留学必須のカリキュラムが魅力的だった
新設の国際経営学部の授業方針に惹かれて入学を決めました。
最先端の研究をしている
少人数制できめ細かい勉強、研究ができるところ
料金(送料含)
:
 350円
350円
発送予定日: 本日発送発送日の3〜5日後にお届け
自ら考え行動するための設備がたくさん備わっているので、やりたいことをやれる。
行きたい内容の研究室があり、オープンキャンパス等での先生方の熱意が伝わりました。
送料とも無料
発送予定日: 本日発送発送日の1〜2日後にお届け
秋田県立大学 システム科学技術学部
最も学びたいロボット工学に関わることを学べる国公立大だから。
教育内容や実験施設が充実している。小人数制で1年から研究出来るから