日本の超小型人工衛星が、新たな「宇宙時代」の扉を開く
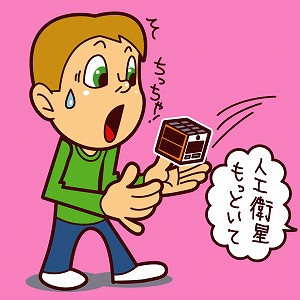
日本の「超小型」人工衛星は世界一
人工衛星というと、国家レベルの巨大プロジェクトを思い浮かべることでしょう。現在打ち上げられている人工衛星の大部分は、国による情報通信衛星や気象衛星、放送衛星などです。これらは重量が数百kgから数千kgもある、中型から大型の衛星で、数百億円もかかります。開発期間も5~7年は必要で、とても民間企業や個人が自分のお金で買えるような規模ではありません。
そこで登場するのが、「小型」を通り越した「超小型」人工衛星という考え方です。
5000万円から可能な「超小型」人工衛星
超小型人工衛星は1~50kgという重量で、5000万~2億円ほどでできます。開発期間は1年半ほどですから、民間企業や個人、自治体レベルでも十分に自己資金で取り組めます。事実、すでに14基の超小型人工衛星が日本で打ち上げられています。実は日本はこの分野で世界一の数と質を誇っているのです。
例えば、2003年6月に打ち上げられた「CubeSat XI-IV(サイ・フォー)」は10cm四方、重量1kgという超小型ぶりですが、現在も立派に稼働しています。2005年10月打ち上げの「CubeSat XI-V(サイ・ファイブ)」、2009年1月打ち上げの「PRISM」も、ともに地球画像を撮影中です。また、2013年には10万個の星の三次元マップを作成する目的で、「Nano-JASMINE」が打ち上げられる予定です。
超小型衛星でしかできないことも
大型衛星1基の代わりに数百個の超小型衛星を打ち上げれば、同じ場所を周回する頻度が増え、定点観測を密に行えたり、たとえ1基が故障しても大勢に影響がなかったりと、たくさんの利点があるのです。
宇宙空間の利用は、人工衛星開発のハードルが下がることで加速度的に広まるでしょう。それはちょうど、コンピュータが小型化して低価格となり、パソコンとして飛躍的に普及したのと同じです。
そして、地球と人類のよりよい未来のために、日本の技術は、最前線で宇宙時代の扉を開こうとしています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






