美しい砂浜を守りたい! 人工衛星から世界の砂浜を診断

世界中の砂浜が危機に直面している
いま日本をはじめ世界中の砂浜で侵食が進んでいます。原因は、川の上流にダムがつくられ海に運ばれる砂が減ったことや、海岸に人工の建造物ができたために侵食と堆積のバランスが崩れてしまったことなどが考えられます。砂浜が浸食され減少していくと、そこに生息する生き物への影響や、人がレジャーを楽しむ場所がなくなるなど、いろいろな問題が生じます。また、砂浜の減少はすなわち国土が減少することでもあります。国や自治体も土砂管理などの対策をとっていますが、適切な対処をするためには、まず現在の砂浜の状態を知る必要があります。
レーダー衛星から砂浜を診断
海岸線の位置を調べその変化を知るために、以前は実際に海岸線を歩きGPSで測定していました。しかし日本の海岸線は長く、定期的な測定も必要なため、コストがかかりすぎます。そこで、合成開口レーダー(SAR)と呼ばれるレーダーを搭載した人工衛星の画像から海岸線を抽出する手法が開発されました。
SARは地表に電波を発射し、その反射波をキャッチして画像に変換します。そのため雲がかかっていても、夜でも画像データを得ることが可能です。しかしSARの画像は、反射の強い陸地は明るく、弱い海は暗くというように、反射波の強弱を白黒で表したものなので、通常のカラー画像に比べて海岸線の判別が容易ではありません。
AIでSARの画像から海岸線を抽出
SARの画像解析にはAI(人工知能)の技術を使います。SARで撮った画像データとそれに対応する実際の海岸線のデータを大量にAIに学習させ、SARの画像から海岸線の特徴を抽出します。そして最終的にはSARの画像のみから海岸線を自動的に抽出できる技術の開発が進められています。
現在の砂浜の状態を診断して、侵食や堆積のデータを集めることができれば、50年後100年後の砂浜の侵食を予測して有効な対策が取れると期待されます。衛星からの診断は、美しい砂浜を守るための第一歩なのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
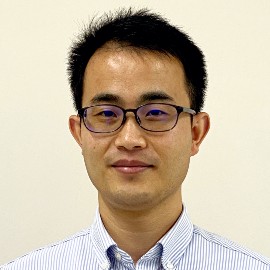
東京海洋大学 海洋資源環境学部 海洋資源エネルギー学科 助教 吴 連慧 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
海岸工学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?





![選択:[SDGsアイコン目標14]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-14-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )




