離島航路の危機を救うために、何ができるのか
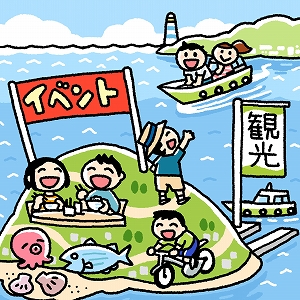
離島航路の危機
島国である日本は、北海道・本州・四国・九州の「本土」と、本土に付属する「離島」によって構成され、本土と離島間、あるいは離島同士の交通は主に船が担っています。離島のうち416が有人で、その多くが高齢化と人口減少という課題を抱えています。近年は利用者の減少や燃料高騰などに加え、船員不足などにより、離島航路の便数の減少や、さらには事業そのものが廃止されたりする事例も出てきました。本土でもバスや鉄道の減便・廃路が続いていますが、タクシーやデマンド型交通といった選択肢が残されています。しかし離島と本土、離島同士を結ぶ手段は基本的には船しかなく、これが絶たれれば離島での暮らしは成り立たなくなります。
人を呼び込む
離島の人口減少は進む一方ですが、離島航路を維持するためにできることはあります。例えば島民の理解を得た上でイベントなどを開催し、交流人口を増やすことも離島航路の安定につながります。人口減少により民間事業者が撤退し、航路が市営化された大分県津久見市の保戸島では、島を挙げたイベントが実施されています。また、福岡県宗像市の大島では、SNSを活用して観光客を呼び込むなど、航路を維持するためにさまざまな手段を講じて着実な成果につなげています。
離島航路を守る意義
少子高齢化や働き手不足、都市部への人口流出などにより都心部との格差はますます拡大し、離島での暮らしは厳しくなる一方です。しかし、国境や海域を保つ役割を果たし、ほかの地域にはない独自の文化を伝えるなど、離島が果たしている役割は決して少なくありません。何より、たとえ不便になっても、住み慣れたところで暮らし続けたいという人々の思いは、尊重されるべきものです。日本の社会課題が、最も顕在化しているのが離島です。離島と本土、あるいは離島同士を結ぶ離島航路について考え、存続の道を探すことは、全国の「地域」の持続可能性を高める上でも大きな意義があるのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )
