苦難の歴史から生まれた、フィンランドの福祉政策と政治システム
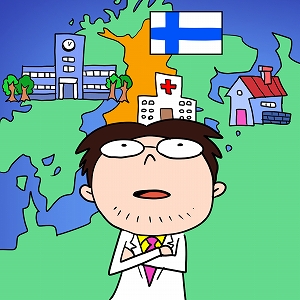
前提が大きく異なる福祉政策
フィンランドは北欧型の福祉国家です。福祉政策はすべての国民が対象となるため、国が提供する福祉サービスも非常に幅広く設定されています。例えばフィンランドでは、就学前教育から大学院の博士課程まで、誰でも無償で教育を受けられます。また、医療機関も非常に安い費用で受診できるほか、育児休業制度が充実しており、住宅を安く買ったり借りたりできるようになっています。フィンランドでは、福祉を日本のように「困っている人を助けるもの」とはとらえておらず、むしろ将来への投資と考えて施策を考えているのです。
なぜ福祉国家になったのか?
フィンランドは、苦難の歴史を歩んできた国です。国境を接しているスウェーデンやロシアの支配を受けたこともあり、1つの国家として独立したのは1917年のことでした。また、第二次世界大戦では、ソ連の攻撃を受けて敗戦、賠償金の支払いや領土の割譲を強いられました。そうした環境の中で、フィンランドが最重要課題として掲げたのが「独立国家の維持」です。すでに福祉国家として体制を築き始めていた隣国のスウェーデンを参考に、国内で産業構造の大転換が始まった1960年代、自国でも手厚い福祉政策を行おうとしました。その結果、現在のフィンランドにつながる「人を大切にした新しい社会」の仕組みが整えられていきました。
手厚い福祉政策を支える政治の仕組み
そうしたフィンランドの福祉政策を支える政治は、多党制が採用されています。各党の支持基盤が国民の各層に分散している上に、常に連立政権が誕生するため、政治がうまく機能していない場合は政策を動かせなかった党が落選するなど、国政の調整機能が働きます。このような多党制は、多様な立場にある人の声が反映されやすく、新しいことにも柔軟に対応しやすい仕組みです。社会の変革期にある現在、多くの国にとって参考となる先進的な取り組みがフィンランドの国内で行われていると言えます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )






