何が起こっているのか? 顕微鏡で「強い金属」の内部を見る
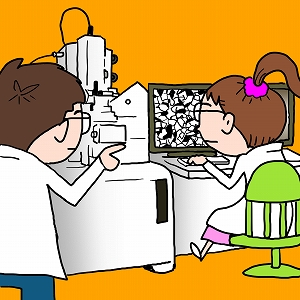
顕微鏡で金属の内部構造を調べる
金属は人間の生活に欠かせない材料で、強い合金をつくる研究が古くから行われてきました。その方法は「金属の配合、熱、圧力の加え方を変えてみて、できたものの強度を測る」といった実験の繰り返しでした。
しかし、電子顕微鏡などナノレベルで「見る」技術の発達で、金属内部の組織を調べる「金属組織学」の研究が盛んになりました。同じ金属でも内部組織が違うと性質が変わること、つまり「どういう組織構造だと強くなるか」という原理がわかってきたのです。
金属の内部で何が起こっているか
金属材料は、すべての原子が格子状に規則正しく並ぶ結晶になっているのではなく、たくさんの結晶の塊が不規則に集まっています。また、原子の格子の中には「転位」と呼ばれる欠陥、つまり穴のような部分があり、それが移動していくことで金属が変形します。転移の移動が起きにくい構造が「強さ」を生むのです。
転位の移動を起きにくくする方法の一つは、混ぜ物をすることです。例えばアルミニウムの中に、シリコンやマグネシウムなどを0.5パーセント程度混ぜると、結晶の構造が変わり、転位が動きにくくなることがわかっています。
量子力学的計算も
また、転位の移動は結晶と結晶との境界で止まります。つまり、たくさんの境界をつくれば、変形しにくい強い材料になるのです。強い金属材料の内部を電子顕微鏡で見ると、細かなツブツブが観察できます。これは「析出物」という小さな結晶の塊で、これが多いほど転位の移動を止める境界が増えるということです。例えばアルミニウムでは、成型した後に一定の温度で置いておく熱処理で析出物の大きさや量が変わることがわかっており、顕微鏡画像を分析しながら目的に応じた熱処理の方法が研究されています。
最近では、こうした分析に量子力学的な計算を用いる研究も始まっており、より精度の高い分析ができるものとして期待されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標7]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-7-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )

