実は身近にいる! 日本近海に暮らす小型鯨類の生態を追う
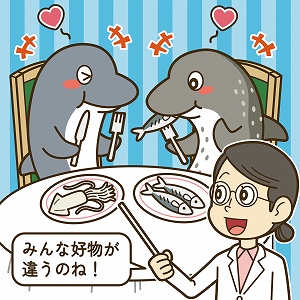
イルカによって異なる食性
日本の近海にはイルカなどの小型鯨類が暮らしています。実は身近な動物であり、日本の貴重な自然であるイルカやクジラがどのような生活をしているのかを明らかにしようと、研究が行われています。
その一つが食性の調査です。日本近海には20種類を超える小型鯨類が生息していますが、それぞれの食性には大きな違いがあることがわかりました。例えば、主に夜に浅い海へ上がってくる深海魚を食べる種、イカばかり好んで食べる種、いろいろな餌を食べる種などです。こうした食性の違いにより、小型鯨類が生態系でどのような役割を果たしているのかが明らかになりつつあります。
駿河湾に来る世界でも珍しいクジラ
日本近海の小型鯨類の生態調査の一環として、駿河湾の小型鯨類の観察調査が行われています。駿河湾には季節ごとにさまざまな小型鯨類が訪れますが、中でもアカボウクジラと呼ばれる外洋性のクジラが陸地近くまでやってくるのは、世界的に見ても珍しいことです。駿河湾は湾内に深海がある特殊な地形であるため、潜水が得意なアカボウクジラが湾内へと入ってくると考えられます。駿河湾の鯨類調査は現在は船からの観察によって行われていますが、日本各地に住む小型鯨類との関係性の解明をめざして、今後は遺伝的な調査も行われる予定です。
知床のシャチの生態を追う
近年、北海道東部、特に知床にシャチの群れが定期的に回遊してくることがわかりました。シャチは日本のほかの地域では定期的な回遊が確認されておらず、保全のためにも早急な生態の調査が求められています。
シャチの背びれの後ろにある「サドルパッチ」と呼ばれる白い模様は一頭一頭形が異なるため、個体識別が可能です。これまでに約600頭が識別されており、群れの構成や行動範囲、群れに新しく生まれたシャチと群れからいなくなったシャチの数のバランスなどが調べられています。今のところ危機的な状況ではなさそうですが、シャチの寿命は約50年と短くないため、長いスパンでの調査が必要です。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
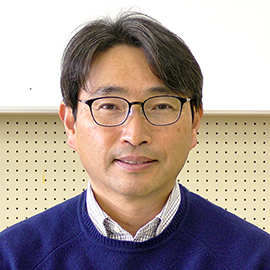
東海大学 海洋学部 海洋生物学科 教授 大泉 宏 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
海洋生物学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標14]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-14-active.png )
