10言語学
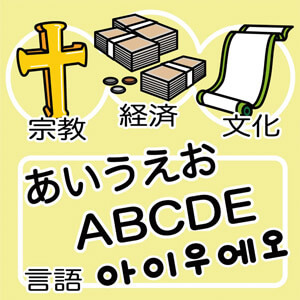
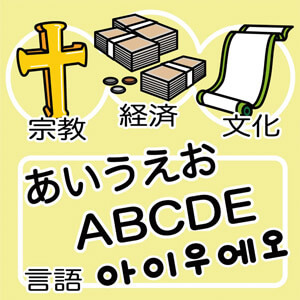
世界には約7,000もの言語があります。言葉はどのようにして生まれ、どんな形で発達していったのか? 人間の大きな特徴である「言語」について、その定義や歴史、どのような機能を果たしているかを、科学的に研究する学問。特定の言語あるいは多種類の言語について、言語の構造や理論、言語の成り立ちや習得過程を研究するとともに、その言語が使われている地域の文化・文学・政治・経済・宗教・社会情勢など幅広い観点から研究します。
さまざまな言語が持つ共通の特徴や性質に注目して、人間の脳の言語習得・知覚のメカニズムを明らかにし、言語習得法を開発するなどの研究や、人間が物事を認識する上で、言語がどんな役割を果たしているかの解明を行う研究もあります。研究には心理学や社会学、教育学などの広範な知識が求められます。
旅行・観光業界、エアライン関連、商社、外資系企業を含む一般企業で活躍する人が大半ですが、専門知識を生かせる職業として、英語教諭や各種言語の教師、翻訳家・通訳になる人もいます。また、外交官をめざす人もいます。

東京大学 文学部 人文学科 教授 西村 義樹 先生
英語の小説の訳書に「オレンジ色の猫」という表現がありました。疑問に思った言語学者の鈴木孝夫先生が調べてみたところ、スペクトルの中でorangeと「オレンジ色」が指せる範囲は、中心では重なっているものの、全体として合致しているわけではないことがわかりました。orange catは、<オレンジ色の猫>ではなく、<明るい茶色の猫>だったのです。
文法における受動態も同様で、「太郎は花子に叱られた」のように、どんな言語の受動態でも表現できる範囲もあれば、「太郎は花子に泣かれた」のように、一部の言語でしか受動態で表現できない範囲もあります。
受動態とは本来、主語が動詞の表す行為によって影響を受ける、という意味を表します。「太郎は花子に叱られた」の場合、対応する能動態の文「花子は太郎を叱った」も「太郎」が影響を受けたという意味を含んでいます。しかし、「太郎は花子に泣かれた」という文に対応する能動態の文「花子は泣いた」には太郎はそもそも登場しません。「太郎は花子に泣かれた」の意味に含まれる太郎が受けた影響とは、花子が泣いているところに居合わせた太郎が経験した迷惑感だと考えられます。このような迷惑感を受動態で表すことができるのは日本語の個性だといえます。
言語の使用を可能にする知識は、語彙(ごい)と文法に分けることができます。語彙の単位を言語学では「語彙項目」といい、「それぞれの言語の丸ごと覚えなければならない表現の単位」を指します。しかし、単独の語彙項目(「犬」、「猫」など)だけでは伝えたいことを自由に表現することができないため、複数の語彙項目を組み合わせて新しい文(例えば、「犬が猫を追いかけていた」)を作り、理解することを可能にする仕組みとしての文法が必要になります。「認知言語学」ではその文法の知識の単位(名詞、動詞、主語、二重目的語構文など)自体にもそれぞれ意味があると考えています。

九州大学 共創学部 共創学科 准教授 李 暁燕 先生
言語の習得は世界とつながる行為の代表的なものだと言えるでしょう。言語は、世界のとらえ方や社会的アイデンティティなど文化を象徴し、表現しています。例えば、日本語環境で必ず毎日言う「いただきます」は、あえて訳せば、英語なら「Let's eat」、中国語なら「我開動了」となりますが、これらは「食べ始めましょう」という意味であって、「いただきます」の本来の意味とは異なります。「お肉も魚もお米もすべて命のあるもので、その命をいただく」という感謝の気持ちを表す文化的な意味は、訳されていません。
言語文化はダイナミックな知です。文法や発音の仕方など、言葉で説明できるものを「形式知」と言います。それに対して、言葉で置き換えることが難しいとされる「暗黙知」もあります。価値観、思考パターンなどの文化的知識はほとんど暗黙知です。例えば、日本語にオノマトペ(擬音語・擬態語)がたくさんあります。「ぷよぷよ」と「ぷにょぷにょ」は音が似ていますが、日本人ならそれぞれのイメージがすぐに浮かぶと思います。しかし、日本語を学習する外国人にはなかなか区別ができません。オノマトペは五感のイメージを表す感性的なものです。そのイメージが暗黙知であり、日本語母語話者でも説明することが難しいのです。
グローバルに活躍するには、現地の文化を理解した上で言語を流暢に話す能力が求められます。翻訳アプリが非常に便利になってきた現在、情報のみの交換であれば簡単にできるようになりました。しかし、お互いが本当にわかり合えるためには、それぞれの文化を尊重し、理解することが重要です。言語を学ぶことは、言葉の裏にある「暗黙知」に留まる文化をも理解することです。暗黙知には、言語に変換できる部分と変換できない部分があります。言語に変換されにくい暗黙知については、体験・実践を通して身につけていくことができます。それらを身につけることで、コミュニケーション能力はより向上します。
大学で西洋史を専攻したいと思い、ぴったりな学習環境を提供してくれる大学。
伝統ある史料編纂所に興味を抱いたから。
人文学がやりたかったので、言語学や心理学、史学や哲学まで幅広く学べる大学に行きたかった
文学部があり、文学や史学、言語学に限定されず社会学や地理学など幅広い学問を1年次に学び、専攻を決めることができるから。
語学学習が充実していたり、学部を横断して自らカリキュラムを組んだりできるという点を魅力的だと感じたから。
多くの外国人留学生と交流しながら、国際感覚を磨きつつ、文化の消滅に限らず、あらゆる国際的な問題の解決策を考えることができる
北海学園大学 工学部
三系列に分かれているので自分の履修したい科目を重点的に学べる。
プログラミングなど、自分が学びたい内容が充実している。