生物に学ぶ情報ネットワークの未来像
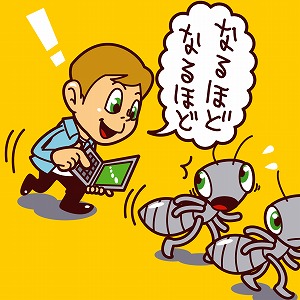
キーワードは「サステナブル」
現在のインターネットシステムは2020年頃には破綻すると言われており、新しいネットワークの構築が求められています。いま世界はサステナブル(持続可能性)な社会のあり方を模索していますが、ネットワークの世界でも同様です。次々と新しい通信機器やアプリケーションが登場する中で、ネットワークも進化、成長し、予期しない事態にも対処できることが求められています。
アリが教えてくれるネットワーク構築
そこで注目されるのが、生物の「自己組織化」です。自己組織化とは、それぞれの個体が限られた情報とシンプルなルールに基づいて動作し、相互作用することで、全体としてうまく機能する現象です。
アリは巣とエサ場との間で一番近い道を通ることが知られています。アリはエサを見つけるとフェロモンという化学物質を地面に残しながら巣に戻ります。次のアリはそのフェロモンに惹きつけられることでエサ場にたどり着き、またフェロモンを残しながら巣に戻ります。短い道ではアリは早く巣に戻ってこられるので、たくさんのフェロモンが溜まり、さらに多くのアリを惹きつけるため、ほとんどのアリが最短ルートをたどるようになります。また、突然最短ルートが使えなくなっても、新しい道をうまく見つけることもできます。このような自己組織化の仕組みを情報ネットワークに利用すれば、複雑で変化するネットワークの中で、効率のよいルートを選び出すことができるのです。
新たな価値観でつくる
ほかにも優れた自己組織化の仕組みを持つ生物がたくさんいます。東南アジアにいるホタルの群れは同期して発光することが知られており、これを参考にした省エネなネットワーク制御の研究が進んでいます。また、豹(ひょう)の模様の仕組みや、大腸菌の代謝の仕組みを使った技術も開発されています。
自己組織型のネットワークは、必ずしも最適ではないですが、規模の拡大や変化への対応、障害に対する耐性に利点があります。新たな価値観に基づくネットワークとして、実現する日も遠くないでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

大阪大学 基礎工学部 情報科学科 ソフトウェア科学コース 教授 若宮 直紀 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
情報科学、生物情報工学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
