薬の研究開発は効き方や副作用をコンピュータで解析・予測する時代に
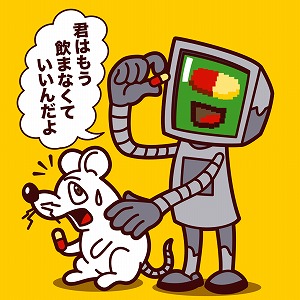
世界中で蓄積されたデータを組み合わせて分析する
開発途中の薬の効果を調べるというと、動物や人間に実際に投与して、その結果を分析するというイメージを持っている人が多いかもしれません。しかし、最近の薬の研究開発の現場では、世界中の医療機関や研究機関で蓄積されたデータを使って、コンピュータ中に患者さんを作りバーチャルな世界で分析する「モデリング・シミュレーション」という手法が取り入れられています。
薬の効果や、体内でどう運ばれるかを予測する
モデリング・シミュレーションで分析するポイントには、大きく分けて2つあります。1つめは、「生体(患部のたんぱく質)に人工的に作成した有機化合物(薬の成分)がくっつくか、くっつかないか」です。2つめは、「薬が体内でどのように運ばれるか」という薬物動態です。
薬は小腸の膜を透過し体内に吸収されると、肝臓へ運ばれ酵素で代謝・分解されます。肝臓で薬の成分が完全に分解されてしまうと、薬が全身の循環に回らず、患部に届きません。また、その人の持つ遺伝子の型(遺伝子多型という)によっては、効き方にばらつきがあるため、この個人差も開発段階でシミュレーションします。例えば日本人では、肝臓のある代謝酵素の数が少ない人の割合が高く、血中濃度が高くなりすぎて「副作用が出やすい」ということが起きます。これも動物や人間に投与される前に予測できるのです。
研究段階でも、臨床でも、薬剤師の役割が大きい
今後、研究段階ではコンピュータによる解析がますます重要になってきますし、臨床の現場では、薬の飲み合わせや、その患者さんの酵素の多い少ないなどのデータにより、薬の投与量を決める時代が既にやってきています。
「川上」に当たる薬の研究段階でも、「川下」になる薬を患者さんに投与する医療の臨床現場でも、高度な知識を備え、コンピュータを使いこなせる薬剤師の存在は欠かすことができないと言えるでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

横浜薬科大学 薬学部 薬科学科/臨床薬学科 教授 千葉 康司 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
薬学先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





