鉱物の「熱蛍光現象」の新たな可能性
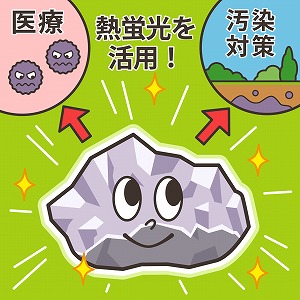
熱蛍光研究の歴史
放射線を受けた鉱物に熱を加えると、浴びた放射線の分だけ光を放出する「熱蛍光」と呼ばれる現象があります。その現象そのものは、17世紀から知られていました。そして、その特性を生かして、20世紀半ばには、放射線の量を測定できる線量計が開発されました。熱蛍光を応用した線量計は現在も使用されていますが、材料や使用法に大きな発展は見られず、熱蛍光現象自体の研究は、あまり進んできませんでした。
熱蛍光による線量計の精度
放射線の線量計としては、熱蛍光を応用したもの以外にも、半導体検出器など、さまざまな原理のものが開発されてきました。その中で、熱蛍光線量計は、正確さや精度に欠ける線量計であるとされ、限定的な用途にしか使用されてきませんでした。そのため、新たな技術が生まれず、長らくこの分野が脚光を浴びることがなかったのです。しかし近年、熱蛍光でも精度の高い計測ができることがわかりました。
熱蛍光を観測するとき、従来は早く結果を知るために、早く温度を上昇させる方法がとられてきました。ところが、温度上昇を遅くすることによって、詳しい特性がわかるようになり、現象の再現性を飛躍的に向上させることができるようになったのです。
医療、そして汚染対策に
熱蛍光を活用する分野として、最も期待されているのは、がんなどに対する放射線治療ですが、それ以外にも、さまざまな用途に応用することができるでしょう。
例えば、福島の原発事故による影響を測定する際、樹木や地面の放射線量を測るのに、安価な測定手法として、熱蛍光物質を使った測定法が新たに開発されました。セラミックスを主体とした板状の熱蛍光線量計は、地面や樹木に刺して測定することができ、今まで正確に測定できなかった、樹木の内部などの汚染状況を生木のまま把握するとともに、汚染が表面から浸透したものか、根から吸い上げたものかなども判別することができます。こうした環境汚染対策のほかにも、社会のニーズに対応した新しい利用法が、今後も登場する可能性が期待されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

東京都立大学 健康福祉学部 放射線学科 教授 眞正 浄光 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
放射線計測学、放射線化学先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





