らせん磁気構造の謎に迫る 物質の性質をひも解く物性物理学
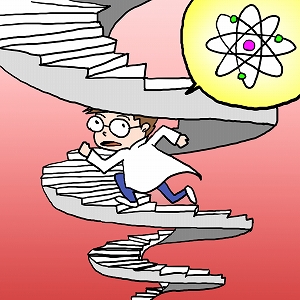
物性物理学とは
物性物理学は、物質の性質を扱う学問です。電気を通す・通さないといった物質の性質の違いは、電子の集団的な振る舞い方に起因しています。電子が集団としてどういう状態を作っているか、その状態が物質の性質とどう関係しているかを理解することが、物性物理学の目標です。例えば、水は温度の上昇によって、氷という固体から、液体、水蒸気という気体に変化します。このような変化は相転移と呼ばれており、温度の違いによって水分子の集まり方が変わるために起こります。なぜ、どのように起こるのかを理解するためには、物質を構成する電子の集団としての動きを詳しく調べる必要があります。
電子の並び方が磁性を決める
電子は一つ一つが小さな磁石の性質を持ちます。それがどのように並び、どんな秩序構造(磁気構造)をとっているかによって物質の磁性が変わります。磁石につく・つかないという性質の違いも、物質内部の電子集団がつくる状態の違いによるものなのです。磁気構造は、原子の並び方である結晶構造と強い関連があります。例えば二酸化マンガンのように、ある種の結晶構造を持つ物質にはらせん状の磁気構造をとるものもあります。らせん構造は崩れやすく、外部から磁場をかけるなどの方法で電子の相互作用を少し変えただけで磁気相転移を起こすなど、特異な性質を示します。
らせん磁気構造の謎を解く
らせん磁気構造は、X線や中性子散乱という方法による観察を通じて観察できます。しかし、らせん状にねじれようとする働きがどこからきているのかなど、本当のところはまだわかっていません。仮説はありますが、実験で検証されていない段階です。検証のためには、さらに高純度の試料を作り、ごく微小な領域を観察しなければなりません。磁気構造の観察には主に中性子線が使われています。しかし、らせん磁気構造の詳細を観察するためには、元素の種類に左右されずに極小のビーム径が使えるといったX線の長所を生かす必要もあり、実験手法の精錬が進められています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

広島大学 理学部 物理学科 教授 松村 武 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
数物系科学、物性物理学、物理学先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標5]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-5-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標16]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-16-active.png )
