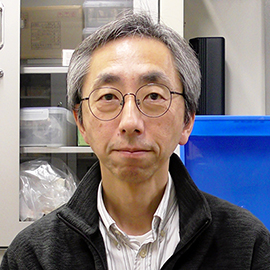マツタケはなぜ高級キノコになった? 人工栽培に向けた挑戦

マツタケとトリュフの共通点
マツタケやトリュフは、どちらも樹木と共生する菌根性キノコという種類で、人工栽培の方法が確立されていません。数が少ない上に山から採取するしかないため、価格が高くなります。
しかし、マツタケは最初から貴重だったわけではありません。20世紀初頭の日本では年間1万トンのマツタケが収穫されており、特に西日本のアカマツ林でたくさん採れました。しかし20世紀中盤以降に外来生物による病気が広がり、マツ枯れという現象が大規模に起こります。共生する樹木が減った結果、21世紀にはマツタケが年間30トンほどしか採れなくなってしまいました。
マツタケの人工栽培に挑戦
マツタケの減少を食い止めようと、マツとマツタケの苗を人工的に育てて山に戻す取り組みが始まりました。まず、マツタケのもとになる菌をシャーレの上で育て、ある程度大きくなったら小さなマツが生えた培養容器に移植します。容器の土にマツタケの菌を入れると少しずつ伸び、やがてマツと共生を始めます。3年ほど育てた苗を土ごと山に植樹すると、マツタケが育ちやすい環境になることがわかってきました。
菌が定着しやすい環境をめざして
マツタケの移植には、まだ大きな課題が残っています。菌が伸びる速度が遅く、共生が始まる前に別の菌や微生物の妨害を受けやすいことです。そのため苗に使う土も、山から採取したあと一度殺菌し、もともといた菌を排除しなければなりません。また、山に植えたあとにマツが別の菌を共生相手に選んでしまい、マツタケの菌が排除される例もありました。それでも苗の段階でマツと共生させてから山に戻したほうが生き延びる可能性が高いため、取り組みが続いています。
マツタケは完全に根付けばほかの菌が入れないほど強固な縄張りができ、何十年も採取し続けることが可能です。その状態に至るまでのプロセスがわかれば、マツタケを増やしやすくなるはずです。マツタケの発生地を調査し、さらに効率的で確実な人工栽培のヒントを得ようと研究が続いています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報