「環境を守る」の新常識 微生物が主役の世界
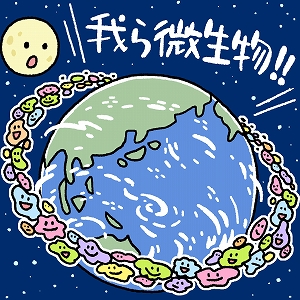
時間と空間を扱う生態学
自然環境の保全というと、特定の生物種の保護に注目しがちですが、実際には生態系の多様性やゲノムの多様性を維持することが重要です。なぜなら、環境の変化に対応できる力は、さまざまな役割を持つ生き物がいることと、その生き物たちが持つ遺伝子の多様さから生まれるからです。
これらの多様性を維持するために、現在の生物環境を把握し、未来を予測したうえで、望ましい未来のために管理することが必要です。そこは、生物が暮らす時間と空間の広がりを対象とする生態学の出番なのです。
生態系を支える微生物
水辺の植物の茎には「バイオフィルム」と呼ばれる微生物の集まりができます。このバイオフィルムの中で、まるで小さな生態系のように、さまざまな種類の微生物が暮らしています。珪藻(けいそう)や藍藻(らんそう)などの光合成を行う生物、それを食べる原生動物、さらには有機物を分解する細菌など、それぞれが役割を分担しています。このような微生物の働きは、水質の浄化や栄養分の循環に重要な役割を果たしています。私たちが目にする規模の大きな生態系は、このような目に見えない小さな生態系によって支えられているのです。
世界の支配者
小さな生態系を支える微生物たちは、地球環境を支配しているとも言えます。例えば、海の中では植物プランクトンなどの微生物が光合成の90%以上を担い、陸上でも50%以上を占めています。また、微生物の呼吸によるCO₂排出量は、人間の化石燃料の利用による排出量をはるかに上回るのです。
微生物は、病気を引き起こす一方で、私たちの体内で消化を助けたり、害虫から守ったりする働きもあります。また、発酵食品の製造や土壌の栄養分を作り出すなど、食料生産にも欠かせません。さらに、環境中の有害物質を分解し無毒化する能力も持っています。このように微生物は、目に見えない場所で物質の循環を支え、地球環境のバランスを保っています。環境保全のためには、微生物を知ることが必須なのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

公立鳥取環境大学 環境学部 環境学科 教授 吉永 郁生 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
微生物生態学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標14]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-14-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )




