遺伝子組換えで微生物の力を強化し、効果的な環境保護対策を
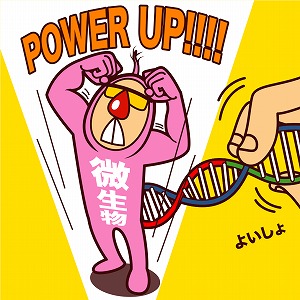
有害化学物質を微生物の力で分解
ヨーグルトやチーズなどの発酵食品はもちろん、医薬品や農薬、洗剤など、私たちは生活のさまざまな場面で「微生物」の力を活用しています。例えばチーズを作るのに使われる「レンネット」は子牛の胃からとられていましたが、今ではカビや組換え微生物によって作られています。
また、環境保全にも微生物は利用されています。環境を汚染している化学物質、例えばポリ塩化ビフェニル(PCB)などの有機塩素化合物などを微生物に分解させて処理しようという取り組みです。
遺伝子組換えで微生物をパワーアップ!
化学物質を分解できる微生物は、生息環境に適応するうちに、「偶然」そういう能力を得てきました。その力をパワーアップさせるため、微生物の遺伝子の、化学物質の分解に関わる部分だけを組み換え、能力を強化する研究がたくさん行われています。私たちが食物を消化・分解し、エネルギーとして代謝するのと同じく、微生物も化学物質を代謝しています。その「代謝」をつかさどる遺伝子を増強することで、微生物をパワーアップさせるわけです。
例えば、PCBを分解できる2種類の微生物についてそれぞれの分解能力に関わる遺伝子を組み合わせることで、さらに分解する力が強いスーパー微生物を作ることができるのです。
植物由来の高分子材料も
汚染物質を分解するだけではなく、汚染の原因になる物質を「作らない」ために、微生物を活用する研究も進んでいます。紙おむつに使われている高分子吸水材の多くは石油から作りますが、これを植物から微生物の力で作れば石油エネルギーへの依存を下げ、環境への負荷を小さくすることができます。これは「バイオリファイナリー」と言われる技術で、バイオエタノールなどもそのひとつです。例えば、パンやビールなどを作る際に使われる「酵母」をパワーアップさせ、植物由来の高分子素材を作り出そうというのです。
さまざまな微生物の力と、それを増強する遺伝子組換え技術の研究がさらに進歩すれば、より効果的な環境保護対策が実現するでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

別府大学 食物栄養科学部 発酵食品学科 教授 陶山 明子 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
応用微生物学、遺伝子工学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )
