暗号を読み解く名探偵が、ゲノムから生物の特徴を探る!
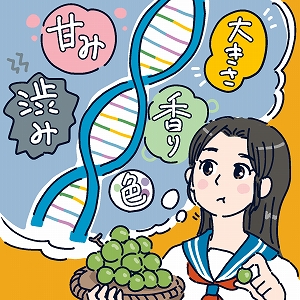
文字から生物の特徴を探る
生き物の体の中には、「DNA」と呼ばれる、とても細長い“情報のコード”が入っています。DNAは、アデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)という4つの“文字”のような物質でできており、「AT」や「TC」のようにさまざまな順序で並んでいます。この文字列こそが「遺伝情報(ゲノム)」と呼ばれ、生き物の体のしくみや性質を決定する重要な情報です。DNAの長さは生き物によって異なりますが、人間では約30億文字にも及びます。この膨大な情報をコンピュータで解析するのが「生命情報学」という分野です。専門家はこの情報を読み解き、生き物の特徴や機能を明らかにします。
独特な風味はなぜ生まれた?
「甲州(こうしゅう)」という日本固有のブドウのゲノムを解析した研究があります。甲州は白ワインの原料として使われますが、少し渋みのある味わいが特徴です。研究者はこの理由を明らかにするため、ヨーロッパのブドウと遺伝情報を比較しました。その結果、甲州のゲノムには「ポリフェノール」という成分を作るための特徴的な遺伝子が含まれていることがわかりました。ポリフェノールは渋みのもとになる物質で、甲州特有の風味に関係していたのです。
ゲノムから生物の正体がわかる
世界中で解読されたゲノムはデータベースに保管されています。これを活用すれば、ゲノムをもとに生物の種類を特定することが可能です。近年では、都市の空気中をただよう「エアロゾル」に含まれるDNAを調べることで、そこに存在する生物の情報が得られるようになっています。たとえば、ある調査では、都市の空気中に含まれる数千種類の植物の花粉が確認され、特に4月から5月にかけてスギ花粉のDNAが多く検出されました。これは花粉症のピークと一致しています。花粉の飛散源がわかれば、花粉の少ない品種への植え替えなど、将来の花粉症対策にもつながると期待されています。このように、ゲノムの知識はさまざまな分野と結びつき、社会課題の解決にも貢献しています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )

