未来のエネルギー革命 薄くて曲がるペロブスカイト太陽電池

新たな太陽電池
次世代の太陽電池として「ペロブスカイト太陽電池」の研究が進められています。ペロブスカイトとは鉱物の一種で、その特徴的な原子配列を模した有機ペロブスカイトが利用されています。この物質は非常に黒く、光を効率よく吸収するため、ごく薄い膜でも発電が可能です。さらに、軽量で柔軟性があることから、屋根だけでなく壁面や曲面にも設置できるため、新たな活用方法が期待されています。また、現在主流のシリコン太陽電池と比べて、製造時のエネルギー消費が少ないという利点もあります。
高効率な二酸化チタンの開発
ペロブスカイト太陽電池は、光を吸収するペロブスカイト層と、そこからプラスとマイナスの電荷を引き抜く層で構成されています。その中で、マイナスの電荷を運ぶ役割を果たすのが二酸化チタンです。二酸化チタンの性質は、その結晶構造によって大きく変わります。例えば、原子の並び方によって炭素がダイヤモンドやグラファイトになるように、二酸化チタンも結晶構造が異なると電気の流れやすさなどが変化するのです。これまでは2種類の結晶構造が利用されてきましたが、より効率のよい結晶構造の二酸化チタンが新たに開発されて、さらなる発電効率の向上が期待されています。
現在、企業と連携した大規模な試験が進められていますが、実用化には劣化が大きな課題となっています。発電効率の低下を防ぐには、どの部分がどのように変化して、発電にどう影響を及ぼすかを解明する必要があります。
持続可能な未来へ
人類が必要とする電力は、地球に降り注ぐ太陽光エネルギーのわずか10万分の1を利用するだけで十分にまかなえると試算されています。つまり、太陽はその10万倍ものエネルギーを地球上に供給しているのです。この豊富なエネルギーを確実に活用するために、ペロブスカイト太陽電池をはじめとする新技術の導入が不可欠です。こうした技術の発展により、持続可能なエネルギー社会が実現できるでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
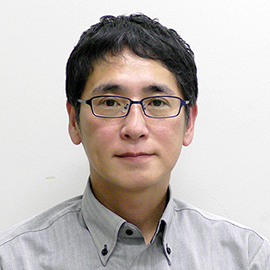
東海大学 理学部 化学科 教授 冨田 恒之 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
エネルギー化学、無機材料化学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標7]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-7-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )


