イカ墨を太陽電池の材料に! 資源活用で環境問題解決に貢献

イカに関するごみ問題
北海道の函館市は、イカの漁獲量が多い街です。しかし肝臓や墨などは、水産加工場の産業廃棄物として大量に捨てられています。ごみの量を減らすためには、捨てられてしまう部分を新たに活用するのが効果的です。そこでイカ墨を未利用資源として役立てるための研究が始まりました。
イカ墨の正体を探る
まずはイカ墨の正体を明らかにしようと、分子を観察できる原子間力顕微鏡を使って観察が行われました。するとイカ墨は液体ではなく微少な粒子の集まりであるとわかりました。まるで工業製品のように、ほぼ均一なサイズの黒い粒子の集まりなのです。
サイズが均一であるという特性は、色素増感太陽電池という次世代太陽電池の部品作りに役立ちます。この太陽電池には二酸化チタン製の、穴がたくさん空いた電極が使われています。穴の数が多いほど吸収できる光が多くなり、発電効率が上がります。しかし均一な穴がたくさんある電極を作るには、多くの手間がかかっていました。一方イカ墨を使うと、簡単に性能のいい電極を作れます。
イカ墨から電極を作る
その作り方は、二酸化チタンの粒子とイカ墨を混ぜ合わせ、高温で焼くだけです。するとイカ墨の粒子だけが分解され、均一な穴がたくさん空いた電極ができます。イカ墨は熱に強いという特性があるため料理にも使われていますが、450度まで加熱すると完全に焼けて消えてしまいます。しかも450度はちょうど二酸化チタンの粒子が固まる温度でもあります。また、イカ墨の色も太陽電池の性能向上に一役買っています。黒は光を吸収しやすく、より多くの電気を生み出せるからです。このような点からも、イカ墨は電極の材料にぴったりだといえます。
ほかにもヘアカラー剤やインクなど、イカ墨からさまざまなものを生み出そうと研究が続いています。用途が広がれば広がるほど、ごみだったものが資源になる可能性が高まります。環境問題解決に貢献するために、イカ墨以外にも未利用資源活用の研究が進められています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
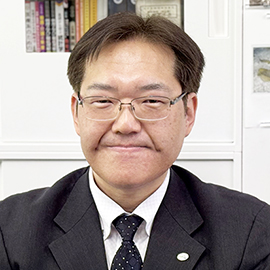
先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標14]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-14-active.png )



