身の回りの電子機器をもっと高性能にするICの新材料
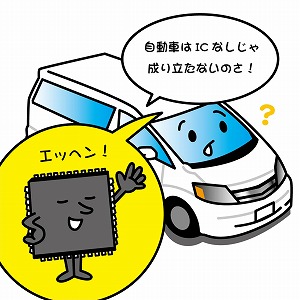
ICは現代技術の心臓部
私たちの生活に身近な携帯電話やゲーム機、パソコン、テレビ、LED、太陽電池などあらゆる電子機器に、IC(集積回路)が使われています。ICは、条件によって電気を通したり、通さなかったりする性質を持つ半導体でできているためICのことを半導体と呼んだりもします。
ICの中には、オンオフの切りかえができるスイッチが多いときは1000億個ほども並んでいます。それらを組み合わせて、計算やデータの記憶、情報の出し入れができるのです。
自動車はICの固まり
自動車はICの固まりとも言えます。エンジンの制御はもちろん、パワーステアリング、ドアロック、エアバッグ、オーディオ、カーナビなど、自動車はもはやICなしでは成り立ちません。
そのIC一つひとつの性能を上げようと、材料の研究が行われています。いまICに使われている材料は「シリコン」が主流ですが、次世代の材料の一つとして注目されているのが「シリコンカーバイド(炭化ケイ素が原料の半導体)」です。シリコンカーバイドはシリコンに比べ、耐熱性、処理速度、省エネに優れています。自動車に搭載するなら、約400℃の高温でも安全に動作しなければなりませんが、その点、シリコンカーバイドは最適です。その上、小型化や燃費の向上も可能なのです。
実用化に向けた2つの課題
いいことずくめのシリコンカーバイドですが、今のところ、価格がシリコンの約100倍するため価格の低下が課題です。また、効率のよい生産方法も確立されていないので、大量生産ができません。
実は、シリコンカーバイドを使ったものは、エアコンなどの一部製品で使われていますが、本格的な実用化はこれからです。自動車だけではなく、パソコンなどさまざまな家電や太陽電池、工場の生産システムなどで、高性能化、小型化、省エネ化の切り札として期待されています。価格の低下と大量生産という課題をクリアしたとき、シリコンカーバイドのICは一気に普及することでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






![選択:[SDGsアイコン目標7]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-7-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )








