工学の技術を医療に生かす ~超小型機械・マイクロマシンの研究~
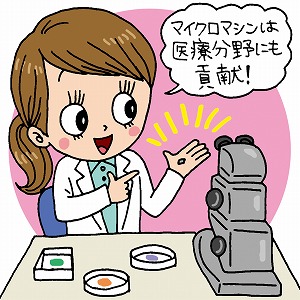
精巧な加工技術をモノづくりに生かす
「マイクロマシン」と呼ばれる超小型機械が、身近なシステムの中で活躍するようになりました。例えば、スマートフォンやゲーム機のコントローラーの中で動きを検知するセンサーなどです。マイクロマシンの基礎となる技術は、細かな電子回路を作る半導体の加工技術(マイクロ・ナノ加工技術)です。マイクロマシンは医療分野でも生かされています。
創薬や再生医療などに役立つ装置
「細胞解析デバイス」は、微小な電極や流路などを数センチのシリコン基板上に構築し、細胞培養や計測を行う装置です。例えば、神経疾患の患者さんの細胞からiPS細胞を作り、培養して神経細胞に成長させます。すると、その神経細胞も、神経疾患の性質を持ちます。それに薬の候補となる物質を投与し、細胞からの電気信号を計測することで薬の効果や副作用を調べるのです。細胞培養から薬の投与、効果測定までが、ひとつのシステムで実施可能になります。細胞は体の中にある時と体の外に出した時では状態が変わってしまうので、体内と同じような環境をどのようにして装置内に構築するかが課題となります。このような装置は、創薬だけでなく、再生医療のために細胞の成長を制御する技術や、化粧品の安全テストなどにも使えます。
血液検査が簡単にできる装置
もうひとつは、血液検査が簡単にできる装置です。これは、幅1ミリ以下の細い流路を作り、その中に血液を流して、血球と血漿(けっしょう)を分離します。そして、血漿中のタンパク質を計測するのです。小さな病院では、血液を臨床検査会社や大病院に送らなければ、検査結果がわかりません。しかし、この装置を使えば、小さな病院でもすぐに結果がわかるようになります。しかも、採血は微量で済むので、患者さんの負担が軽くなります。この装置を使った検査キットが安価で手に入るようになれば、在宅医療や過疎地域の医療に多いに役立つでしょう。
このように、最先端の工学技術で作るマイクロマシンは、医療分野に貢献できる大きな可能性を秘めているのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

九州工業大学 大学院生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 教授 安田 隆 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
機械工学、電気電子工学、マイクロナノ工学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
