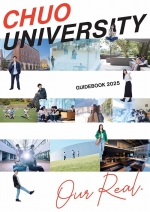「格差」と「貧困」をなくすための経済のあり方

富の偏りが招く、「格差」と「貧困」
世界中の富の約半分は、1パーセントの裕福な人間が所有していると言われています。それだけ富が偏っている、つまり、「格差」が大きいということです。格差が拡大すると、貧困の人も富裕層も増加することになります。「貧困」とは、アフリカなどの開発途上国だけに発生するものではなく、日本でも、貧困のために衣食住が満たされない人、さらには餓死をする人すら出ています。格差が広がれば、日本でもこうした貧困が増えていくことになります。
循環システムで貧困を解消する
アフリカなどでの貧困問題は、国全体の技術や教育が遅れているために起こります。一方、日本などの先進国における貧困は、国としては富んでいても、富の分配がうまくいっていないために起こるものです。このような貧困を解消するためには、地方で生産したものを大都市圏で消費するだけでなく、国内で市場が循環する地域循環システムを確立することが大切です。循環は経済において重要な要素の一つです。循環しないと経済は停滞しますが、うまく循環すれば貧困は解消していきます。
「ワーキングプア」が起こるわけ
賃金が相当低くて、働いても働いても貧困から抜け出せない、いわゆる「ワーキングプア」の人が増えています。企業としては利潤を極大化して、成長を図ることが当たり前です。しかし、利潤を追求するあまり、労働者に支払う賃金を引き下げたり、雇用を不安定化させたりすることで、不安な生活を送らざるを得なくなる人々が増加しています。国も、若者を使い捨てにするような企業への監視を強め始めています。
こうした状況を改善するためには、行政だけでなく、経営者の意識改革も必要になります。「一番の資産は人間である」という考え方に立ち、「雇用者」という人的資本に投資するという意識が求められているのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

中央大学 経済学部 経済学科 教授 松丸 和夫 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
経済学先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?