道路に島をつくると安全で快適になる! 「二段階横断」の効果とは
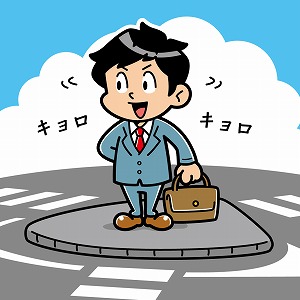
歩行者の事故が多い日本
交通事故で亡くなる人の中で、歩行者の割合が高いのが日本の特徴です。ヨーロッパでは20%前後ですが、日本は35%程度です。特に道路横断中、左側から来る車にはねられるケースが多いという統計があります。車が右から来る手前側の道路は渡るタイミングを掴みやすいのに対し、奥の方は左からの車の速度を読み違えて渡り始めてしまい、ぶつかるという実態があるのです。
横断しやすく、車もゆっくり
ヨーロッパでは「二段階横断」が広く使われています。二段階横断は道路を一気に渡るのではなく、真ん中に「交通島」というスペースを設けて2回に分けて渡る仕組みです。信号機のない横断歩道の場合、左右を何度も確認しながらタイミングを探らなくてもまずは片側を確認すれば渡れますし、島で立ち止まって再び確認して渡るので、それぞれ横断チャンスは増えます。
実際に二段階横断の安全性が検証されました。道路を撮影した動画のAI(人工知能)画像解析やデータ解析を行った結果、島に人がいる場合は70%の車が止まり、島がない道路よりも高い確率で道を譲ってくれることがわかりました。しかも駅前では95%にまで高くなりました。横断施設(横断歩道や交通島)に近づく車のスピード自体も平均で時速3.9km遅くなるというデータも取れました。二段階横断は、歩行者の利便性が高まる上に、車が譲ってくれやすいメリットがあるわけです。
道づくりはまちづくり
二段階横断に関する日本のガイドラインはまだ定まっておらず、協議、研究段階です。横断施設はただ多ければいいというわけではなく、歩行者が使いたい場所にないと意味がありません。スクールゾーンなど設置場所によっては、歩行者の安全意識の向上にも繋げられます。ドライバー側の視点も必要で、海外にある横断歩道とセットではない「島」だけを作る手法も日本で使われるとよいでしょう。ちょっとした工夫で信号機に頼らなくても事故が少ない円滑な道になり、ひいては道づくりから安全な都市・まちを組み立てることができるのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

名古屋工業大学 工学部 社会工学科 環境都市分野 教授 鈴木 弘司 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
交通工学、交通計画学、土木計画学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )

