月面で暮らすための「ものづくり」を支える熱流体工学
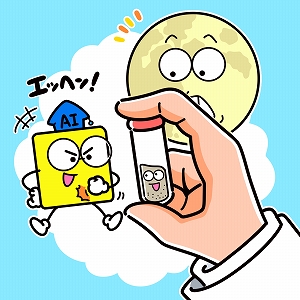
月の砂で家を建てる
2030年代、人類は本格的な月面探査に乗り出します。将来、多くの人が月で暮らすようになれば、地球から建材を運び続けるのではコストがかかりすぎます。そこで注目されているのが、月の砂をブロックなどの建材にして活用する方法です。月面の建物には、放射線や100℃以上の温度変化などに耐える性能が求められます。溶かさずに砂を焼き固めるだけでは性能が不十分なため、溶かして固める必要があります。ただしそれには膨大なエネルギーが必要で、それを省エネルギーで実現できるプロセスを設計する必要があり、そのためのシミュレーション技術の研究が進んでいます。
月特有の課題に挑む
月でのものづくりのためのシミュレーション技術には、地球環境を前提に作られてきた技術を刷新する必要があります。砂が溶けて再度固まるプロセスは「マルチフィジクス解析」と呼ばれる分野で研究が進んできていますが、月の重力は地球の6分の1しかないため、地球では重力の影響に隠れていた表面張力などの現象が顕著に現れます。また、溶けた月の砂の表面張力などの物性値データが整備されていないことも課題です。このことから、溶けた月の砂の物性値を国際宇宙ステーションに搭載された静電浮遊装置で測定する実験が計画されています。
新たなAI技術と熱流体工学の融合
月の砂の溶融凝固プロセスのような複雑な現象をシミュレーションするには、「どの方程式を計算すれば良いか」が分からないことがあります。また、実験データを得る機会も限られます。このような問題に対して、物理法則に基づいた新しいタイプの「物理ベースAI」が注目されています。従来のAIが大量の教師データを必要とするのに対して、この物理ベースAIは圧倒的に少ないデータから学習できます。また、「どの方程式を計算すれば良いか」を学習で知ることも出来るようになります。この技術は、熱流体工学以外にも幅広い分野に適用でき、未来社会の発展に寄与すると期待されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )

