4つの心音を聴き分けろ! データで病気を把握する生理機能検査
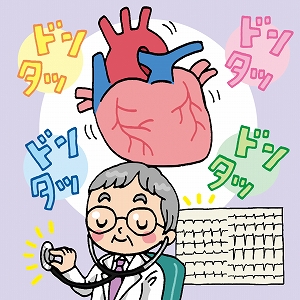
体に機器を装着してデータを収集
「生理機能検査」は、臨床検査の中でも独特な分野です。血液などの検体を対象にするのではなく、臨床検査技師が患者に対面して行う検査で、患者の体に直接機器を装着して、電気や音などの生体情報を収集します。循環器系の生理機能検査では、心臓が動く際に生じる微弱な電気信号を記録して、その活動を波形として可視化する「心電図」検査があります。
また、超音波を利用した「エコー」検査もあります。超音波とは耳には聞こえない高周波の音波で、これを体に当てて、その反射音を解析することで画像を作成します。例えば心臓エコーでは、心臓の弁の動きはもちろん血管径の測定も可能です。またドップラ血流計では血液の流れる速度なども知ることができます。
4つの音が混じる心臓の音
心臓の音は、一般的に「ドッタン、ドッタン」と繰り返し聞こえますね。この、「ドン」「タッ」という2つの音は、実際には4つの音が重なっています。心臓には、右心房、右心室、左心房、左心室の4つの部屋があり、それぞれの弁が開閉する音と血液の流れる音が聞き取れます。例えば弁の大きさによって音の高さも異なり、大きな弁は低い音、小さな弁は高い音を出します。このように生体から発する「音」にも非常に多くの情報が含まれています。熟練した医師は、聴診器を使いこれらの音を聞き分けて驚くほど精密な診断を行っています。
患者に負担の少ない検査
生理機能検査では通常の検査のほかに、患者に運動負荷をかけて心電図の変化を観察する運動負荷試験などがあります。しかし、具合が悪くて来院した患者にとって、階段の上り下りや自転車をこぐなどの運動は体への負担が大きく、患者の具合をさらに悪くしかねません。そのため「生理機能検査学」では、患者の体への負担をできる限り軽減しながら正確に病気を把握することをめざして、運動負荷によるエネルギー量を数値化できないかなどの研究も行っています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
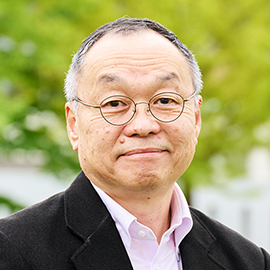





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
