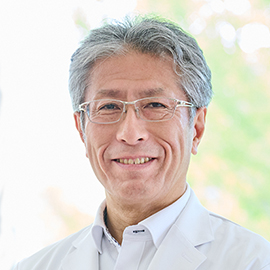「病気を見つけ出す」臨床検査技師が酵素の謎の働きを解き明かす

医師の診断を支える臨床検査技師の仕事
医師が診断を下す際、患者の顔色や脈拍など臨床で得られる情報以外に、心電図検査や血液検査などのデータが不可欠です。その検査データを提供するのが臨床検査技師で、医師の診断を支える重要な役割を担っています。つまり、臨床検査技師は「病気を見つけ出す人たち」だといえます。
臨床検査は、大きく分けて「検体検査」と「生理機能検査」があります。検体検査では、血液中の成分を化学的に分析して、赤血球や白血球の数、血糖値などを測定します。一方、生理機能検査は、電極や機器を用いて患者の体から得られる信号や画像を分析する方法です。「臨床化学検査学」は、血液などの検体を分析して、病気の診断や治療に役立てる学問です。
50種類以上の成分
血液検査では、試験管のキャップの色が検査項目によって異なる仕組みになっています。例えば、紫色のキャップは赤血球や白血球数の測定、グレーのキャップは血糖値測定など、どの病院でも同じ色のキャップが使われています。このような工夫によりミスを防いで、効率的に検査が行えるようになっています。
血液中には、多くの成分が含まれています。血液を遠心分離機にかけると、比重に応じて層に分かれ、赤血球などの重い成分が下部に、血漿(けっしょう)などの軽い成分が上部に分かれます。上澄み成分は、上清(じょうせい)と呼ばれます。
まだ解明されていない血液中の成分
上清にはさまざまな成分が含まれており、これらを分析することで、病気の有無や進行状況を調べることが可能です。しかし、その働きや病気との関連性が不明なものも存在します。例えば、ある酵素は病気になると必ず変動しますが、なぜ変動するのか、分子レベルでのメカニズムは解明されていないのです。このような「素性のわからない」酵素の働きを明らかにすることは、臨床化学検査学の重要な研究テーマとなっています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報