「先生、知ってる?」 子どもの目を輝かせる秘密
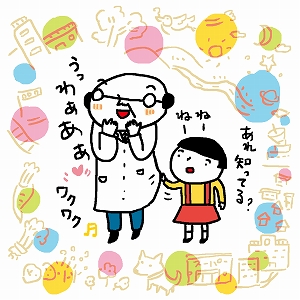
自分の「?」をもつこと
街を歩いていて、ふと「信号機の色はなぜあの並びなんだろう?」と思ったことはありませんか? 調べてみると思いもよらない理由が隠されています。自分でもった疑問は、先生から与えられるものより、強く印象に残ります。それは、主体的な学びだからです。社会科では身近な疑問から社会の課題まで、自分で調べ、話し合っていくことで自分では気づかなかった人々の働きや工夫が見えてきます。こうした学習過程で一番大切なのは、「?」を自分のものにしているかどうかです。
2度体験をさせるとよいわけ
子どもが自ら「?」をもつにはどうしたらよいのでしょうか。例えば、スーパーに見学に行くと「なぜこのように商品を並べるんだろう?」「お客さんはどこを見て商品を選ぶんだろう?」など、さまざまな疑問をもち始めます。しかし、初めて訪れた場所では疑問を見つけられなかったり、お店の人やお客さんに質問できなかったりします。しかし、もう一度スーパーに見学に行く機会を作ると、探求心が行動に結びついて、お店やお客さんに話を聞いたり、さらに調べたりするようになります。中には、地域にお店が少なくなって買い物ができない高齢者がいると知り、お店に移動販売をお願いするといった行動をとった実践例もあります。実体験を通した学びによって「自分の目線」から「お店やお客さんの目線」、さらには「地域社会の問題を見る目線」へと見方が多面的に広がっていったのです。
先生のワクワクが、子どもの目を輝かす
実体験をさせるには、教員はさまざまな下準備が必要です。また、準備と時間がかかるので、学校の教員同士、地域の人々と連携・協力する必要があります。準備を進める中で「子どもたちは驚くだろうな」「新しい?を見つけるかな」と子どもたちの顔が次々に浮かんできて先生はワクワクしてくるでしょう。先生がワクワクしたものは、子どもたちにも伝わり、目を輝かせてくれるはずです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

椙山女学園大学 教育学部 子ども発達学科 教授 相川 保敏 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
教育学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )



