「クスリのリスク」を回避する 「薬物動態」と「薬の形」の研究
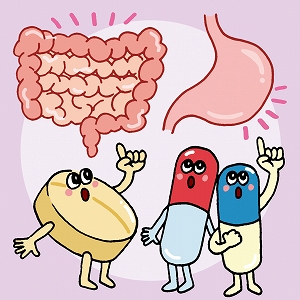
薬のカタチはどうやって決まるのか?
現在、製薬会社が開発する薬のほとんどが錠剤、つまり「経口固形剤」です。その特長は、携帯に便利なこと、量の調節がしやすいこと、コストが安いことなどが挙げられます。
ただ、弊害もあります。それは、小腸で吸収されて血流にのった薬の成分が、意図しない臓器に運ばれてしまうと副作用のリスクがあるのです。薬はターゲットとなる臓器以外では、副作用が起こるリスクが必ずあります。そこで、副作用が起こる臓器に薬が到達しないように、塗り薬や吸入薬という形になることもあります。
吸収された成分が体の中でどう動くか
副作用のリスクを知るためには「薬物動態」を調べます。薬の成分が吸収されて体内に広がり、代謝されて排せつされるまでに何が起こるかを明らかにするのです。その上で、例えば薬の成分が「小腸で吸収されてしまう」とわかれば、小腸で吸収されない形に設計するのです。
その実例の一つが、潰瘍性大腸炎の薬剤成分です。薬物動態の研究で、その成分は口から飲むと小腸で吸収されてしまい、大腸まで届かないことが判明しました。そこで、大腸だけに存在する酵素で溶ける素材でその成分を包んだところ、小腸を通過して大腸まで届くという結果が出ました。今後は、薬として発売するための研究が行われていきます。
機能性表示食品にも応用
こうした製剤設計のノウハウは、サプリメントや機能性表示食品、化粧品の開発にも使われています。単に健康によい成分を製品に入れるだけでなく、体の中でより効果を発揮する工夫をするのです。例えば、成分を胃で溶けやすくすることで、小腸での吸収率が10倍になった例もあります。
こうした改良が可能になった背景には、成分をナノレベルで加工する「ナノテクノロジー」があります。これまでは新たな薬剤候補となる成分が開発されても、副作用や吸収性の問題で薬にならないケースもたくさんありましたが、ナノテクノロジーによって、新たな薬や機能性食品がたくさん開発される可能性があります。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
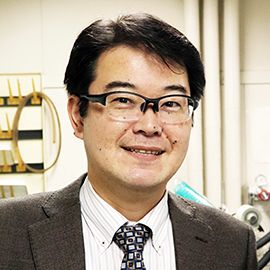
先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )




