海の温暖化対策はサンゴから!

サンゴの「白化」とは
サンゴは海中の植物のように見えますが、実は動物です。触手や口や内臓を持ち、体内には「褐虫藻(かっちゅうそう)」という光合成を行う藻類が共生しています。サンゴは褐虫藻が光合成で生み出す栄養を受け取り、褐虫藻に必要な窒素やリン等を提供することで共生が成り立っています。ところが近年、海水温の上昇により、褐虫藻がサンゴから排出されることでサンゴが白く見える「白化(はっか)」という現象が世界各地で見られます。白化が進むとサンゴは栄養を得られなくなり、やがて死に至ります。サンゴの死は、サンゴ礁で暮らすさまざまな生物にも影響が及んでしまいます。
意外と歴史の浅いサンゴ研究
サンゴと褐虫藻との共生は2億年以上前から始まったと言われていますが、共生のメカニズムが注目されたのはごく最近のことです。1998年、エルニーニョ現象で大規模な白化が起きた際に注目が集まり、研究が急速に進みました。白化に光と温度が関係していることや、褐虫藻にも種類があることが明らかになったのもこの頃です。近年では、ストレスに強い褐虫藻や、サンゴの栄養になるような細菌を与えることで、白化を抑えようとする研究も行われています。
共生のプロセスを解き明かす
白化の直接的な原因は褐虫藻が光合成時に放出する活性酸素で、それが海水温の上昇にともなって増えることがわかっています。一方で、褐虫藻がサンゴの体内で共生を始め、関係を維持する仕組みは大部分が未解明のままです。
そこで、サンゴが誕生してから褐虫藻を体内に取り込み、共生に至るメカニズムを調べる研究が続いています。人工的に受精させたサンゴの幼体に褐虫藻を与えて、さまざまな遺伝子の変化を解析していきます。中でも注目されるのが「消化」のプロセスです。サンゴは体内に入る異物を、通常は免疫反応で攻撃して消化しますが、褐虫藻の一部はその過程をくぐり抜けて共生に至ります。この現象のメカニズムの解明が、今後の白化対策につながると期待されます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
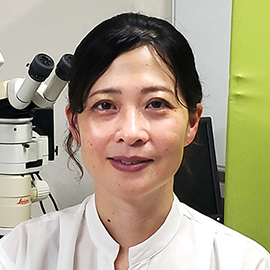
先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標14]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-14-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )

