地球の未来は海の中に 海洋生物が織りなす炭素循環

地球環境を左右する海の炭素循環
海の生物は地球上の炭素循環において重要な役割を果たしています。海の生物の活動は地球上の二酸化炭素を減らす効果を持っており、地球温暖化にも深くかかわります。このように生物は自ら周りの環境を変える力を持ちますが、逆に環境の変化の影響に対してさまざまな応答をすることも知られています。海の仕組みを知り、地球温暖化に対処するために、「環境と生物の相互作用」に着目した研究が進められています。
二酸化炭素の噴き出す場所が教えてくれる未来の海
二酸化炭素の増加という環境変化が海中の生態系に与える影響を調べるために、海底火山などの影響で二酸化炭素が噴き出している海域が研究に活用されています。普通の海ではサンゴやさまざまな生物が豊かな生態系を作っていますが、二酸化炭素が多い場所では生物の種類が減り多様性が失われます。伊豆諸島の式根島にある二酸化炭素が噴き出す場所では、大型の海藻やサンゴが少なくなり、海底に小さな藻類が広がる草原のような景観に変わることがわかりました。
日本全国の海を調査する
海藻は、光合成によって二酸化炭素を吸収し、海藻の体などの有機物を作り出します。沿岸の岩場に生える海藻は、枯れると沖に流され、その一部は深海まで沈んでいきます。深海に沈んだ有機物は海の表面に戻ってくるまでに数百年などの長い時間がかかるため、二酸化炭素を閉じ込める働きをしています。このような沿岸の生物が閉じ込める炭素は「ブルーカーボン」と呼ばれ、地球温暖化を抑える重要な役割を果たしています。しかし、沿岸開発や環境変化で海藻の生息域が減少していることは深刻な問題です。
ブルーカーボンの重要性や実態を知るために、日本各地の「臨海実験所」を活用した大規模な調査や、北海道から九州に至る幅広い海域でデータの収集が進められています。このような研究は世界的にも珍しく、「臨海実験所」が多数設置されている日本だからこそ可能なプロジェクトとして注目されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
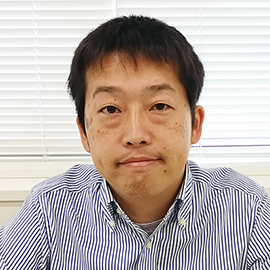
先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標14]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-14-active.png )

