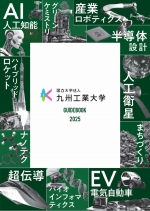遺伝子情報と治療の橋渡しをするバイオインフォマティクス
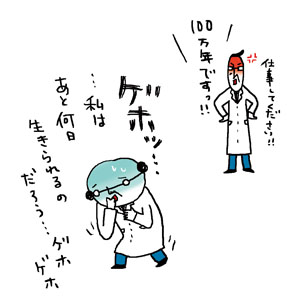
病気診断を可能にする遺伝子発現データ
あまり嬉しい話ではありませんが、近い将来、がんになったとき、あとどれくらい生きられるかを予測できるようになるかもしれません。この判断の基礎となるのが、「遺伝子発現データ」というものです。これは、膨大な生物の遺伝子の中でどの遺伝子がどの程度働いているかを明らかにしたものです。このデータは、マイクロアレイという分析器具によって検出されます。
例えば、複数の前立腺がん患者の遺伝子発現データを検出し、遺伝子ごとに比較します。そうすると働いている遺伝子とそうでない遺伝子の色分けができるようになります。前立腺がん患者の色分けは、一定のパターンを示し、また、そのパターンがどの程度はっきりしているかでがんの進行度も判断できます。この診断で、一見正常な人でも検査によって早期に前立腺がんを発見できるようになります。ただ、実際には患者にも個人差があり、ほかの病気を併発している場合もあります。その場合はデータを読み取ることが難しくなります。しかし、そのようなデータも含めて解析することで、将来的には患者それぞれの病気の総合診断ができるようになると考えられています。
正確で効率的な治療が可能に
この診断が医学に対して与えるメリットは、病気の進行や副作用などの個人差がデータとしてわかるので、正確で効率的な治療を行うことができることです。また、薬の開発にも役立つでしょう。
現在の課題は、「遺伝子発現データ」の分析をさらに進化させ、検出できる病気の対象を広げることです。このような、生物学に情報科学を応用した学問を「バイオインフォマティクス」と言います。人のゲノム(遺伝子配列)は明らかになりましたが、それぞれの遺伝子の生物学的な意味はほとんど明らかになっていません。それは、数が膨大で意味の解析が容易ではないためです。その意味で、遺伝子発現データの解析には、大きな期待が寄せられています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

九州工業大学 情報工学部 生命化学情報工学科 教授 山﨑 敏正 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?