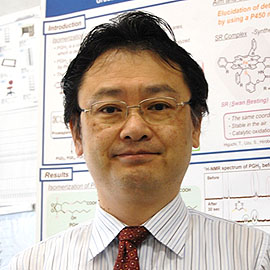みんなが買える薬を作るには?

薬のはじまり
昔の人は、病気を治したり体の調子をよくしたりするために、草木や鉱石、動物などから体によいものを作り、試してきました。これが薬のはじまりです。特に植物から作られるものが多く、中国では生薬、西洋ではハーブとして使われていました。
いろいろなものを試した結果、熱を下げたり、痛みを抑えたり、火傷を早く治すものなど役に立つものが見つかりましたが、逆に毒になるものもありました。薬は、試行錯誤しながら進歩してきたのです。
改良を重ねて、薬は進歩していく
例えば柳の木の枝は、煎じて飲むと痛みが治まったり、熱が下がったり、という効果が昔からわかっており、民間療法に使われてきました。近代になり、柳にはサリチル酸が含まれていることが判明しました。この成分には鎮痛・解熱効果があるのですが酸性が強く、使い続けると潰瘍を起こすなど、強い副作用があります。そこでサリチル酸のヒドロキシ基をアセチル化して副作用を弱め、アセチルサリチル酸として合成する改良を加えました。これが解熱鎮痛剤として、創薬から100年たった今でも使われている「アスピリン」です。副作用は抑えられているのに、効果は十分あり、しかも大量に合成することが可能です。
ただアスピリンにしても、どうして効くのかわからないまま使われ続けていました。1970年代から40年の間に、人の体や原子の結合について研究が進み、なぜ薬が効くのかわかるようになってきました。シクロオキシゲナーゼ(cyclooxygenase)という炎症を起こす酵素が、アスピリンによって阻害されていることがわかったのです。アスピリンは、「自然界で、ある程度効くものを見つける」→「それを改良する」→「合成によって供給できるようにする」という経過で作られた、薬の歴史の典型的な例です。天然の成分は、草木の中にはほんの少ししか含まれておらず、薬の大量生産には向きません。しかし、アスピリンのように石油を原料として合成を工夫し簡単に作ることができると、多くの人に安価で薬を提供することができます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報