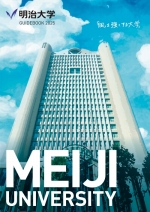史実とは一体何なのか? 金印に秘められた歴史の検証へ!

弥生時代の日本の外交の足跡を示す、あの金印
歴史の教科書に必ず出てくる「漢委奴国王(かんのわのなこくのおう)」と彫られた金印は、江戸時代に発掘された最も小さい国宝で、日本の外交史の扉を飾るものです。
「委」は日本を、「奴国」は現在の福岡平野あたりを意味します。そのすぐ西側の伊都国(いとこく)という国があった場所では中国の前漢時代の鏡が三十数面も発掘されており、伊都国も漢帝国から、最先端の文物を手にいれていたことがわかっています。つまり紀元前1世紀、中国では前漢、日本では弥生時代の中頃から北九州地方は中国と頻繁に往来があり、その中で金印をやり取りするような政治交渉が起こったのです。
「本物 vs 偽物」論争
ところが印面の彫り方に関して、中国の後漢の時代の彫刻技術が江戸時代にも可能であったということを根拠に、金印が偽物であるという学説が出てきました。そこで、金印をいろいろな角度から改めて検討するという作業が2010年から行われ、以下の点が検証されました。
まず、印面に彫られている文字が後漢の初めに特徴的に見られる文字と同じ形態であるということ、そして印のサイズが後漢のものと一致するということ、さらに金の純度や金属組成、ツマミの形、紐孔(ひもあな)の底の凹みも、江戸時代には知りえない事実であるとわかりました。つまり江戸時代の彫刻技術を持ってしても、これらの条件はクリアできないため、偽物の製作は不可能だと考えられます。
過去の資料を再検討することもまた考古学
考古学は、新たに遺跡から発掘されたものを研究することが主ですが、実は江戸時代のような過去に発見され、再び議論の対象となったものをもう一度現代の目で分析する、というのも大事な仕事です。多くの人が確かだと考えていても中には疑問を持つ人もいるため、それを受け止めて議論することが必要です。どの学問分野でも全員の意見が一致することはありえません。疑問を持つ人がいて初めて議論が成り立ち、そこから研究が進むのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

明治大学 文学部 史学地理学科 教授 石川 日出志 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
考古学、歴史学先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?