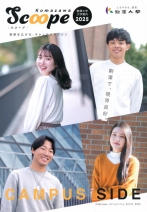5G普及のカギは「オークション」?

5Gの登場
携帯電話などの通信に使われる周波数帯は、政府から通信事業者への免許制で割り当てられます。日本ではデジタル化の進展で5G(第5世代移動通信システム)が登場し、より高速で大容量の通信が期待されます。そこで議論となるのは、「5Gのための周波数帯を事業者にどう割り当てるか」という問題です。
どうやって割り当てる?
5Gでは、4G以前よりも高い周波数帯が使われます。低周波数帯は既に他のシステムで使われており、共用が難しいからです。低周波数帯の電波と比べると、高周波数帯は電波が真っすぐに進み、届く距離が短いという特性があります。そのため、通信事業者は基地局をたくさん設置する必要があり、エリア別の周波数帯の組み合わせを緻密に検討しなければなりません。
一方で政府は、複数の事業者に対して、効率的に周波数帯を割り当てたいと考えています。そこで検討されているのが、政府がオークションを実施して事業者に周波数帯を割り当てる仕組みです。この仕組みは、アメリカでは1990年代から実施されて高い効果をあげており、2023年において日本を除くOECD(経済協力開発機構)加盟国の全てで導入されています。
オークションの理論と実験
周波数オークションの設計には、経済学の一分野である「オークション理論」が活用されています。とくに、特定の周波数帯に入札が集中する事態を避けるよう、研究者によって巧妙なルールが提案されてきました。オークション理論の歴史は古く、ウィリアム・ヴィックリーによる1961年の論文に端を発します。それ以降、「どうすれば効率的に財を割り当てられるか」あるいは「どのようなオークションが売手の収入を最大化するか」といった問題に対して、理論的な解答が導出されてきました。
さらに、生身の人間に被験者として「オークション実験」に参加してもらい、その行動データに基づいて理論の検証がなされています。周波数オークションでも、制度を本格導入する前に、まずは実験でその性能を確かめることが重要でしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報





![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )