進化するものづくりの世界 消費者が満足する製品を作るには?
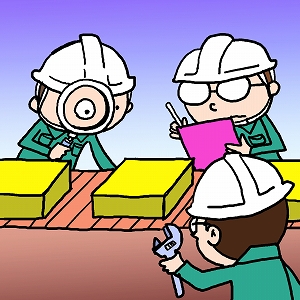
消費者を満足させる「品質管理」
「品質管理」という、消費者が喜ぶような製品やサービスをどう提供するかを研究する学問があります。この研究は、工場で製品を作る際、いかに不良品を作らないかということに焦点をあてて発展してきました。品質の良いものを作っていこうという努力のおかげで、現在は工場での不良品の数が劇的に減っています。しかし、良い製品・サービスがあふれる現代の世の中では「製品が不良品でない」だけでは、もはや消費者は満足できません。製品にかかわるさまざまな人たちが、そろって「品質とは?」ということを考えていかないと、企業が競争に勝ち抜けない時代なのです。
高品質な製品づくりを助ける「QFD」
満足度の高い製品を開発するサポートツールに「quality function deployment(品質機能展開)」(通称:QFD)というものがあります。例えば、テニスのラケットを開発する際、消費者がどのようなラケットを欲しがっているかという意見をアンケートやリサーチなどで集めます。しかし、開発を担当するエンジニアは、その意見を見ただけではどのような製品を作ればいいかわかりません。「壊れにくいラケットが欲しい」という消費者の声を、エンジニアが理解できる技術的な用語や具体的な数値を使った設計図に変換することで、消費者が求めるラケットを作り出すことにつながります。
テーマパークにも「品質管理」は必要
海外の有名テーマパークでもQFDが活用されています。そのパークを作る際、恐竜のアトラクション近くに、動く恐竜のオブジェクトを設置することになりました。アトラクションは「子どもに喜んでもらう」ことが一番のねらいだったので「子どもが喜ぶために、恐竜にどういった感情表現をさせるか」ということを軸に、動物園に通って子どもたちが喜ぶ瞬間をリサーチしました。その結果「子どもは、動物の頭をなでられる・動物と目が合うと喜ぶ」ということがわかったため、それが可能な恐竜を設計し、設置したのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






![選択:[SDGsアイコン目標8]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-8-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )
