助産師の気づきやサポートが、親子を孤立から救う

児童虐待は連鎖する?
児童虐待は世代間で連鎖するという説があります。つまり、親から虐待を受けた経験をもつ人が、自分が親になった時に、自分がされたように子どもを虐待してしまうということです。子どもを愛おしいと思っていても、自分は親のようにはならないと思っていても、自分を虐待した親の影が色濃く残り、子育ての中で過剰な反応として表れることがあります。
虐待の連鎖は宿命ではない
過去に親から虐待を受けた経験をもつ、子育て中の20~30代の母親を対象にしたインタビュー調査があります。そこには、自分が親から受けたのと同様に子どもに虐待をしてしまったケースもあれば、自分が幼少期に満足な教育を受けられなかったことで、自分の子どもにはいい教育をしたいという思いが強くなりすぎて、過剰な期待が虐待につながったケースもあります。
一方で、幼少期に親から虐待を受けたものの、友だちや祖母、親戚など周囲の温かい支援が心に残り、そのおかげで順調に子育てができているという事例もあります。また、虐待をしてしまった場合でも、助産師の産後家庭訪問により支援の手が差しのべられたことで虐待を中止できたケースもあります。親の影を完全に克服することは難しいですが、虐待の連鎖は宿命ではありません。適切な支援があれば断ち切ることができるのです。
社会全体でつくる子育て環境
児童虐待を個人の問題として片づけて、親だけに責任を押し付ける社会では、当事者は孤立してしまいます。そうしないためには、社会全体で支え合う環境をつくることが求められます。妊娠中から出産、育児までをサポートする助産師や、赤ちゃんの健診や育児相談などを担う保健師が連携することで、継続して支援することは可能です。上手に人に頼れずに支援の手からこぼれ落ちた人をすくい上げるのは、親子と接する人たちのちょっとした気づきです。その気づきを見落とさずに支援の手をつないでいく意識をもつ人が増えれば、安心して子育てできる環境が整っていくはずです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
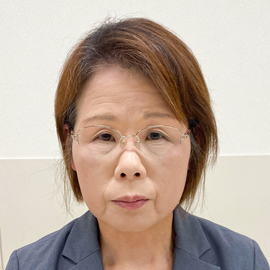
明治国際医療大学 看護学部 看護学科 准教授 坪倉 浩美 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
母性看護学、看護学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標1]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-1-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
