国際文化交流を考える 国家の思惑を超える人と人とのつながり

国際主義の広がり
かつて戦争は国益獲得の有効な手段でした。しかし人類史上初の近代戦となった第一次世界大戦は、多数の死傷者といった負の側面に目が向けられる契機になりました。そこで新たな国益追求の手段として、国家間の協力体制が提案されるようになりました。国際連盟はその好例です。国家間の協力は、戦争を抑止するような体制や活発な貿易体制のみならず、互いの文化を紹介し合うという文化面にも及びました。こうした一連の動きを、国際主義といいます。国際主義の潮流の中で国際文化交流が事業化されるようになり、日米学生会議が1934年に誕生することとなりました。
日米学生会議
日米学生会議で日本の大学生たちは、日本の「満州」政策の「正しさ」を米国人の大学生に知ってもらいたいという目的をもっていました。一方、米国人は集団としての目的をもたず、参加動機は個人で異なりました。しかし唯一共通していたのが、憲兵や特高による検閲に抵抗感をもったことです。米国人学生は、1937年以降は会議に学生以外が立ち入らないようルールを設けることを提案し、これに日本人学生も賛同しました。全体主義下にあった日本で、言論の自由が確保されていた事例は珍しく、米国の自由主義が日本に影響を与えた事例なのではないでしょうか。国際文化交流には人と人が影響を与え合うことで、思わぬ変化を生み出す場であるといえます。
日系二世と国際文化交流
日米学生会議には、多くの日系二世が参加していました。日系二世は米国生まれの米国人ですが、日本から北米に移住した日本人を両親にもちます。当時の米国は人種隔離政策によって、人種的マイノリティが差別される状況にありました。二世たちは積極的に発言し、自らのエスニシティが白人に劣るものでないと承認されることを目指して会議に臨みました。国際文化交流の目的の一つに、国同士の相互理解が掲げられることがあります。しかし日系二世の存在は、時に国際文化交流は「国」という単位では捉えきれない多様性があるということに気づかせてくれます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
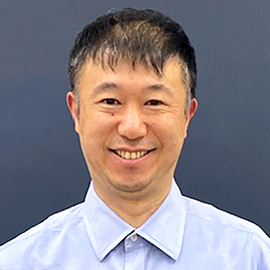
神田外語大学 外国語学部 英米語学科 講師 中村 信之 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
日米関係史、国際関係史、地域研究先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?





![選択:[SDGsアイコン目標5]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-5-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標10]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-10-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標16]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-16-active.png )
