理想と現実の差を攻略せよ! 仮想現実空間で制御する産業用ロボット
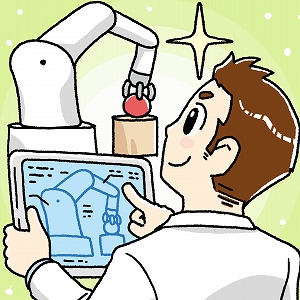
産業用ロボットの進化
日本では1980年代から産業用ロボットが急速に普及しました。産業用ロボットは、モータでアームの関節を動かして、ベルトコンベア上の「ワーク」と呼ばれる部材に同じ加工作業を繰り返すものが主流です。その制御は、人が数値を入力して動作を記憶させる方法から始まり、コンピュータでプログラムした動作データをロボットに転送する方法へと進化してきました。そして現在は、AIで仮想現実空間に作ったロボットの理想的な動作を、実際のロボットに伝える制御が始まっています。
理想の動きと現実の動き
現実のロボット作業にはハプニングがつきものです。例えば、放電の熱で溶接するロボット(アーク溶接ロボット)では、ワークの位置ずれが起きます。常に状態を監視して、仮想現実上のモデルとの差をフィードバックし、ロボットの動きを修正しなければなりません。
アーク溶接ロボットでは、放電に使う電流の変化からワークのずれを検知する方法が開発されており、カメラなどのセンサが不要で画期的な方法となりました。また、ロボットが何かにぶつかったときに検知した力を信号として情報処理を行い、瞬時にロボットの動きを止める技術も開発されています。この技術は、人にぶつかっても危険のない「協働ロボット」の開発にも貢献しています。
より実際に即したモデルづくり
このように、仮想現実空間に設定した理論上のロボットと現実のロボットの動きには差があります。その差を埋める技術は、どのような産業用ロボットでも製品の出来を左右するため、重要な研究対象です。
現在注目されている研究の一つは、より現実に即したモデルづくりです。ロボットを動かすとき、モータやギア、アームには、慣性力やたわみなどさまざまな物理的な力が加わり、動作に影響していますが、それをあらかじめ把握することが難しいのです。それを反映した仮想現実空間のモデルができれば、理想と現実との差のないロボット制御が期待できるとして、研究が進められています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

大阪産業大学 システム工学部 システム工学科 教授 西田 吉晴 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
制御工学、ロボティクス、メカトロニクス先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標8]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-8-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )




