職人技に頼らない、「誰でも」操作できる人工心肺装置をつくる

臨床工学技士とは?
臨床工学技士の役割は「生命維持管理装置の操作」ですが、それ以外の医療機器も幅広く扱います。生命維持管理装置には主に人工心肺装置、人工透析装置、人工呼吸器の3つがあり、それぞれ循環、代謝、呼吸の機能を代行またはサポートします。臨床工学技士はこれらの医療機器の操作を行うことに加えて日頃のメンテナンスも行います。臨床工学技士の特徴として、手術室や集中治療室などの治療の現場で「医師の右腕として直接関わる」点が挙げられます。
人工心肺装置の操作の「属人性」をなくす
多くの臨床工学技士は人工心肺装置の操作にプライドを持っているものです。それは、人工心肺装置の操作が習得に多くの時間を要する「職人技」の要素が高いからです。しかし、人工心肺装置の操作が「経験」に依存しているのは問題です。なぜなら、日本の心臓手術施設の6割では年間症例は100例未満と少なく、その経験を積む機会が限られる施設でも人工心肺装置の使用は求められるからです。少子高齢化に加えて有資格者が少ない中で、人工心肺装置の「属人性」を排除するための研究があります。
人工心肺の仕組みを変える
人工心肺の回路には、回路上に大気に開放された貯血槽を持つ「開放型」と、貯血槽を体外循環回路から分離した「閉鎖型」があります。国内外の医療現場は「開放型」の人工心肺装置をベースに運用されていますが、これは生体内を循環する血液量が操作者による送血流量と脱血流量のバランスで維持される仕組みです。そのため、人工心肺装置を絶えず監視して、変化に応じて調整し続けるための高い集中力と職人技が要求されるのです。そして「開放型」をベースにした臨床研究は多くなされていますが、「回路そのものを変える」領域に踏み込む研究は少ないのです。
そんな中で、「開放型」と「閉鎖型」の間、いわば「中間型」の人工心肺装置が完成しています。これは操作の属人性が軽減されたほか、患者の体にも優しい点が特長です。国内でもすでに導入されている施設があり、注視されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
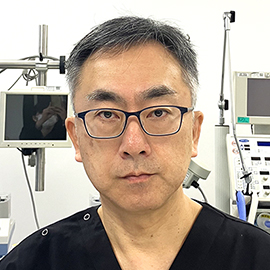
先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )

