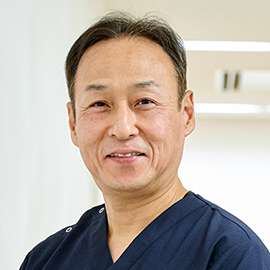細菌は進化する! 感染症対策の最前線

消毒薬が効かない細菌
感染症の治療には抗菌薬が欠かせません。しかし、抗菌薬の服用によって腸内細菌のバランスが崩れ、偽膜性大腸炎を引き起こす細菌が増殖してしまうことがあります。この細菌は保菌者の便を通じて人から人に感染するため消毒が欠かせません。しかし、この細菌は「芽胞(がほう)」と呼ばれる硬い殻を作ることで、アルコールをはじめとする多くの消毒薬に耐性を持ちます。そのため病院内感染対策における重要な課題となっています。さらに近年、在宅医療が推進される中で、患者がこの細菌を自宅に持ち帰ってしまい、在宅環境でも感染が広がる可能性があります。そのため、専門家でなくても実践できる効果的な消毒方法の確立が求められています。
細菌との知恵比べ
現在、この細菌への対策として、複数のアプローチによる研究が進められています。一つは、特定の波長の紫外線による消毒方法の開発です。通常の殺菌灯(254nm)は人体に有害ですが、220nm付近の波長は人体への影響が少なく、殺菌効果も期待できることがわかってきました。しかし、紫外線は光が届かない部分には効果がないため、完全な解決策にはなりません。
また、芽胞を有する菌を殺菌する消毒薬として、一般的には次亜塩素酸が用いられますが、環境汚染や腐食の問題が発生してしまいます。環境への影響が少なく、誰でも安全に扱うことができる消毒薬の開発が求められています。
感染症との戦いは続く
歴史を振り返ると医学の進歩により激減した感染症もありますが、細菌側が薬に対抗する能力を進化させて生き延びることもあります。例えば同じ大腸菌でも、菌株によって効く薬が異なるのは細菌が遺伝子レベルで変化して、薬への耐性を獲得するためです。実際にこのまま耐性菌が増え続けると、2050年頃には感染症での死亡者数が、現在のがんによる死亡者数を上回るという予測もあります。人類と感染症との戦いは、人類の歴史が続く限り終わることはないのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報