代謝をターゲットとした医学研究や食品科学研究の新展開
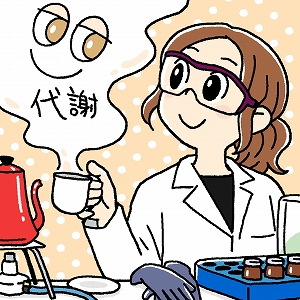
代謝物を網羅的に分析
代謝とは、生物のからだの中で起こっている生命維持のための化学反応で、代謝に関係するアミノ酸や脂質などの生体物質を代謝物と呼びます。生体内での代謝メカニズムについては解明が進んでいますが、代謝物には生体に対する未知の機能があると考えられており、医療などへの応用が期待されます。例えば、がん細胞と正常細胞では代謝が全く違うので、代謝物を測定することで、従来の腫瘍マーカーでは難しいがんの早期発見が可能になるかもしれません。
近年、細胞内の代謝物を網羅的に解析できる「メタボロミクス(メタボローム解析)」という技術が登場しました。1回の測定で百種類以上もの代謝物を分析できるシステムが構築されており、この技術で代謝物の変動の全体像や代謝の変化を知ることが可能になりました。
代謝の観点からのがんの発見・治療・予防
メタボロミクスを使って、がん細胞と正常細胞の代謝物がそれぞれ網羅的に解析されています。がん細胞と正常細胞では増殖のスピードなど機能に大きな違いがあるため、両者を比較してがん細胞の仕組みに新たな発見が得られれば、がん細胞の代謝メカニズムの解明や、がん細胞の代謝制御によるがん抑制へと展開していくことができます。さらに、がん細胞の代謝変動を捉えることで、がんの早期発見などにも貢献できるかもしれません。
微生物の代謝でコーヒーが変わる?
食品の原材料は動植物などの生物であるため、食品の味や香りといった品質や機能性を担う成分は代謝物であり、例えば発酵食品は微生物の代謝を利用しています。そこで、コーヒー豆をインドネシアの大豆発酵食品を作るのに使われるカビ(テンペ菌)で発酵させた後に抽出したコーヒーの品質・機能性について、発酵による変化や代謝との関係を調べる研究が行われています。もし発酵でコーヒーの品質が高まれば、低品質のコーヒー豆の改良につながり、気候変動や病害などが原因でコーヒー栽培の適地が半減するという「2050年問題」にも役立つかもしれません。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
