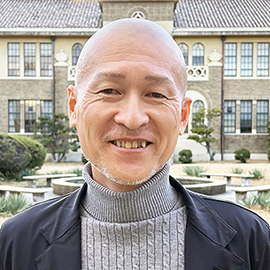雌はなぜ相手を選ぶ? 魚たちの繁殖生態

水流に耐えられるほどのイクメン
多くの生物では、雄と雌に見た目や行動の違いがみられます。この雄と雌の違いは、雌や大切な資源をめぐる雄間競争と異性に対する雌の選り好みを通した「性淘汰(とうた)」によって進化します。ここでは魚類の性淘汰に関する研究を紹介します。
ハゼの多くは雄が子育てをすることが知られており、川にすむヨシノボリもその仲間です。ヨシノボリの雄は石の下に巣を作り、求愛ダンスで雌を巣に誘うのですが、雌は速い流れの中でダンスした雄を好みます。速い流れに耐えて踊ることができる雄は、健康状態が良くて、しっかりと子育てできることから、雌は雄が求愛ダンスを踊る水の流れの速さに基づいて、子育て上手な雄を正確に選んでいると考えられます。
好みがころころ変わるヌマチチブの雌
ヌマチチブは淡水性のハゼの仲間で、やはり雄が石の下に巣を作り、子育てをします。巣作りに不可欠な石が少ない場所では石を巡って雄同士の激しい争いに勝ったものだけが繁殖のチャンスを得られますが、石が多い場所では多くの雄に繁殖のチャンスがあります。
石の多さは雌の好みとも関係します。石が少ない環境では、雌は大きい雄を選びます。大きな雄ほど、巣を作れなかったほかの雄から巣や卵を守ることができるためだと考えられます。一方で、石の多い環境では、雌は背びれの長い雄を好みます。背びれの長い雄には寄生虫が少ないことから、巣を持てない雄が少なく、雄の強さが子の生存とあまり関係のない状況では、雌は背びれの長さで雄の寄生虫への耐性などを判断していると思われます。
男らしさは諸刃の剣
コイ科の淡水魚であるオイカワの雄は繁殖期になると目立つ赤色の婚姻色を示し、赤い面積が広いほど雌に好まれます。体色が赤くなるのは雄性ホルモンのテストステロンの増加によるものですが、それは同時に免疫力の低下を引き起こします。つまり、免疫力が低下しても病気に抵抗できる強い雄が体色を赤くしていることになり、雄の婚姻色を手がかりに雌は病気に強い雄を選んでいると考えられます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。





![選択:[SDGsアイコン目標14]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-14-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )