憧れの「強い存在」とは? 女子プロレスの歴史に潜む多様性
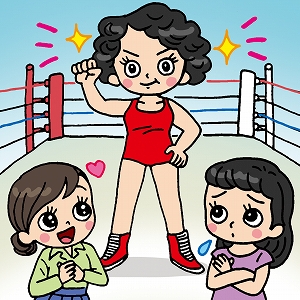
戦後の女性のイメージは?
終戦直後の日本の女性に対して、「お金や物資がなくて苦労した」「妻や母として家庭を支えることを求められた」といったイメージがあるかもしれません。しかし「周囲が憧れを抱くほどの強い存在」として生きた女性たちもいたことが、女子プロレスの歴史研究からわかってきました。
研究では女子プロレスに関する新聞や雑誌記事、大衆小説の分析のほか、選手や観客だった人への聞き取り調査も行われました。その結果、メディアが取り上げた女子プロレスの姿と、女性たちの観点には大きな違いがあります。
メディアと女性の印象の違い
メディアは女子プロレスラーを性的な観点から扱う傾向があり、「露出の多い衣装を着た若い女性がリングの上で暴れている」などの描写をしています。一方女性のなかには、選手を「勇気をくれるヒーロー」のようにとらえた人がいました。
女子プロレスは戦後間もない頃から始まり、テレビでの試合中継をきっかけに1955年頃に第一次ブームが起こります。この時代、太陽族と呼ばれる不良男子グループが若い女性に危害を加える事件が多発していました。そのためリング上で戦う選手を見た女性たちは、「自分の代わりに不良をやっつけてくれそう」「泣き寝入りをせず戦っていいのだ」と、憧れや勇気を抱いたのです。
一方で女子プロレスを「はしたない」「戦わされる選手がかわいそう」と思っていた女性もおり、意見にはかなり幅があったといえます。
歴史に潜む多様性
これまでの日本の女性の歴史研究では「芸能の世界に生きる女性はメディアから性的な目で見られていた」「日本の復興とともに女性は強くなっていった」といったように、ひとくくりにしてとらえられがちでした。しかし女子プロレスの受け止め方だけを見てもわかるように、実際にはさまざまな価値観の女性たちがいて、ときには意見が衝突することもありました。これまでは見落とされがちだった女性の多様性にも注目して、歴史を新たな観点から見直そうと研究が続いています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

神戸女学院大学 国際学部 グローバル・スタディーズ学科 准教授 瀬戸 智子 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
日本近現代文化史、ジェンダー研究先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標5]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-5-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標10]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-10-active.png )





