発達の不思議を「子どもの目で見る世界」から探る
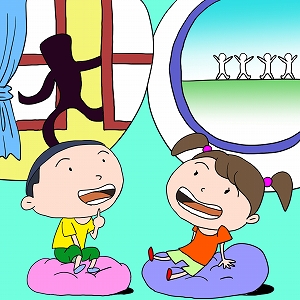
子どもたちの不思議な世界の見方
「小さい子どもって不思議なことを言うな」と思ったことはありませんか? 机の上にできた影を見て「外の影が窓の隙間から飛び込んできたんだよ」という不思議な説明をする子もいます。地球が丸いと習うと「でも地面は平らだよね。きっと地球の中が空洞になっていて、中の平らな部分に僕たちは住んでいるんだ」と真剣に考える子もいます。どちらも変わった考え方に感じるかもしれませんが、これは豊かな想像力の表れです。子どもたちには子どもたちなりの世界の見方があり、自分の経験をもとに想像力を広げて、一生懸命世界を理解しようとしているのです。
具体と抽象をつなぐ発達の架け橋
子どもたちは、身近な体験から目に見えない概念へと理解を広げていきます。これは具体的な経験と抽象的な概念の間に「架け橋」を作っていく大切な道筋です。初めは目に見えて触れられるものを通して世界を理解します。例えば動きのある「風」は感じ取れても、「止まった空気」は理解が難しく、空き箱を見て「ふたが開いているから空気が出ていった」ととらえる子もいます。しかし、年齢を重ねるにつれて、直接触れられないものの存在もわかるようになり、高学年になると「愛」や「平和」といった目に見えない概念も理解できるようになるのです。
子どもの自立を支える発達の理解
2歳児の「イヤイヤ期」は重要な成長の時期です。「靴が履けない!」と泣き叫ぶ子どもに、すぐに手を貸そうとすると「自分でやる!」と怒り出してしまいます。この時、子どもが求めているのは手助けではなく「うまくいかなくて悔しいね、でも頑張っているね」という共感かもしれません。そうした子どもの気持ちに寄り添うことで、子どもたちの中に自分でやってみようという意欲が育っていきます。子どもたちの「自分でやりたい」「自分なりに理解したい」という思いは、人間の根本的な成長の原動力です。心理学は研究を通して、このような人間の発達と理解の不思議な世界を探っていくのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

東北文教大学 人間科学部 人間関係学科 教授 永盛 善博 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
発達心理学、教育心理学、保育学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )




