レジリエンス理論-困難に対する「心の回復力」を探究する
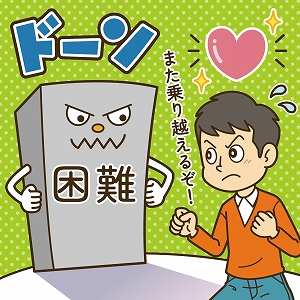
社会心理学とは
社会心理学は、個人や集団が社会にどのように影響を受けているかについて研究する学問です。例えば、大学生を対象にユーモア(笑い)の使い方が情動に与える影響について研究されています。また、中高生のスマホ依存の問題、SNSの使用が人間関係や精神的健康に与える影響に関する研究などがあります。それらの研究は、個々の発達段階における心理的な特徴や問題を理解して、支援や課題解決に役立てることができます。
心の回復力を研究
研究テーマの一つに、困難や逆境に対する精神的な回復力に焦点を当てて、個人の心理的な耐性を研究する「レジリエンス理論」があります。レジリエンス(resilience)とは、「回復力」や「復元力」などと訳される言葉です。このテーマの重要性は、社会や家庭、教育において心理的な支援が必要となるような場面で「どのように人が立ち直るか」を明らかにできる点で、環境的要因や遺伝的な背景がレジリエンスに与える影響が研究されています。現代の心理学における新たなアプローチの一つとして、特に思春期や青年期におけるレジリエンスが注目されており、心理学だけでなく、社会学、教育学などの分野と重なりながら研究が進められています。
データサイエンスとしての側面
「レジリエンス理論」は、主にアンケート調査が用いられています。質問項目には、「問題があったとき、すぐに立ち直る方だと思うか?」「嫌なことがあったとき、どのように対処するか?」といった内容が含まれます。心理学にはデータサイエンスの側面もあり、こうして集まった回答は表計算ソフトを使うなどして統計的な分析を行います。これにより、レジリエンスが高い人と低い人との違いや、その後の回復力の差異が明確になりつつあります。例えば、自己概念がポジティブな人ほどレジリエンスが高く、困難に対してより柔軟に対応できるという結果が得られました。
こうした研究は、精神的な健康維持や心理教育、災害などの心理的な支援策の改善に役立つと期待されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標17]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-17-active.png )







