農業が作リ出した「文化的景観」を守り、地域を活性化したい!

今ある景観を未来まで維持するには?
例えば山梨県の峡東地域では、桃やブドウなどの栽培が行われており、春には一面ピンクの桃の花で彩られます。農業によって作り出された独自性のある景観が観光資源にもなっています。今では国際連合食糧農業機関の世界農業遺産として認定されています。
このような文化的な景観を守り未来へと残していくためには、農業従事者や行政だけではなく、市民の力も必要です。また、公園や緑地の管理にも市民ボランティアが関わっていますが、高齢化によって活動を縮小するところも出てきています。市民の参加の促進が課題ですが、研究により、ボランティアをしたい人と、してほしいところをつなぐ「ボランティアコーディネート」が重要であることが見えてきました。
身近な緑とは?
では人々が守りたいと感じる身近な緑の景観とは何でしょうか。明確な定義がないため、調査が行われました。「風景イメージスケッチ法」を用いて人々が描いたスケッチを分析した結果、樹木や地理・地形、草本・水辺といったものを、身近な緑と感じていることがわかりました。また、調査によって、ボランティア参加者が魅力に感じていることは、運動になること、自然に触れてリラックスできること、環境について学べることなどだということもわかりました。このような研究が積み重なり、市民が環境保全活動に参加しやすくする仕組みが整いつつあります。
環境教育や次世代への伝承にも注目
農学部の学生といっても、実際の農村で暮らしたことのない人は大勢います。そこで、茨城県内で子どもたちの自然体験プログラムを提供している人たちと一緒に、学生たちの「里山の管理体験」が催されました。学生たちが実感したのは、自然を守るには人と人とのつながりが欠かせないことでした。そこで、地域の自然に関する知識や技術を次世代に伝承するための研究も進行中です。
今あるものをいかに残して、現代の暮らしに適応させるか、人々の暮らしや受け継がれてきた文化を含めた「文化的景観」の保全が今、重要性を増しています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
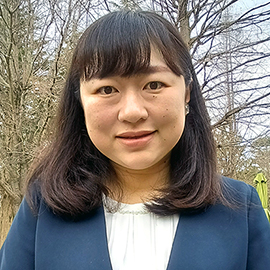
茨城大学 農学部 地域総合農学科 地域共生コース 准教授 高瀬 唯 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
ランドスケープ科学、環境農学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標17]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-17-active.png )
