社会を支える材料開発~将来はシミュレーションで新金属ができる!?
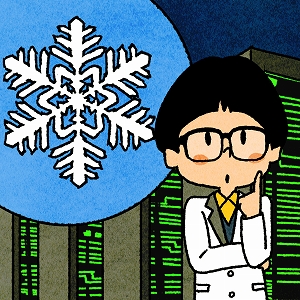
材料開発の膨大なお金と時間
スマートフォン、電気自動車など、新しい機器が次々に生まれていますが、そこには「新材料」が関わっていることが少なくありません。材料開発は、実験による試行錯誤の連続であり、膨大なお金と時間がかかります。この実験による試行錯誤をコンピュータ・シミュレーションに置き換えれば、開発が簡単になります。
特に金属は、高温処理が必要だったり内部が見えなかったりと「観察」が難しいため、溶けた金属が固まるプロセスや内部構造をコンピュータでシミュレーションして可視化しようという研究が進んでいます。
複雑な現象をモデル化
溶けた金属が冷えて結晶化していくとき、条件の違いによって結晶の様相が変わり、それが金属材料の特性に違いを生みます。結晶化のプロセスを計算式でモデル化し、プログラムをつくれば、どのような条件を与えるとどういう特性が生じるかをシミュレーションできます。現段階では、最新のスーパーコンピュータを使用して、「フェーズフィールド法」というシミュレーション手法で結晶成長の可視化にも成功しています。
膨大な計算量
しかし、実用化には大きな課題があります。コンピュータの計算量が膨大なのです。金属内部で起きている現象は非常に複雑で、材料力学、流体力学、機械力学、熱力学などの法則が絡み合います。また、この現象は非常に小さいところで生じていて、例えば直径1ミリほどの金属の中で1万個もの現象が起きています。金属の特性を予測するには、そんな現象の計算を材料として使う大きさまで積み上げる必要があり、スーパーコンピュータでも不可能なほどの計算量になることがあるのです。
その問題を解決すべく、速く、効率的に計算できる、実用的なシミュレーションツールを開発する研究が進んでいます。その先には、仮想空間上でシミュレーション実験を行い、その結果を現実の実験に反映させる「デジタルツイン」を使った材料開発で、より高性能な金属が続々と誕生する未来が来るのかもしれません。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )

