多様な人々が集まる場を、情報技術を使ってデザインする

「ワークプレイス」のデザイン
ワークプレイスとは人々が活動する場所のことです。働くためのオフィスだけでなく、学びを進める学校なども含まれます。ワークプレイスをデザインするには、単に形をつくるだけでなく、さまざまな要素を結びつける必要があります。盆踊りのお祭りに例えてみると、中心となるステージの設計や装飾、そこにかかる予算の設定や実際のお金の調達、音楽の選曲や音響システムの構築、人々に周知する広告などが含まれます。ワークプレイスのデザイナーには、それらすべてをまとめ上げるコーディネーターとしての能力が求められるのです。
情報技術で可能性を高める
ワークプレイスのデザインには情報技術を使ったアプローチは重要です。多様な価値が尊重される現在では、ワークプレイスが均一に割りつけた箱のような空間では、そこにいる人々のパフォーマンスを充分に引き出せません。最新技術によりセンシングした人の動きをコンピュータで解析して、設計を導き出す研究もなされています。例えば教室の座席の配置は、縦横の軸線をそろえて均等に並べるのではなく、授業に向き合う多様性に配慮した並びでもいいはずです。そこで、人の動きの解析をアルゴリズムにしてコンピュータに与え、画一的ではない座席の配置を自動生成させます。多様な人々が一緒になって過ごす場所としては、徹底的に合理性を追求したデザインよりも、無駄や柔軟性を持つ余地のあるようなデザインの方が長持ちし、多彩な可能性が期待できます。使い手側が自由に考えられるような場のデザインが、ワークプレイスでも求められるのです。
空間への応用
実際にワークプレイスデザインを行うには、さまざまな諸条件を処理してデザインにつなげるコンピュータ技術の習得が大きな鍵となるため、プログラミング教育が重要視されます。その一つが、コンピュータプログラムにより造形をしていくアルゴリズムデザインであり、複雑化する問題を解き、新しい創造性を発揮する道具となるものです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
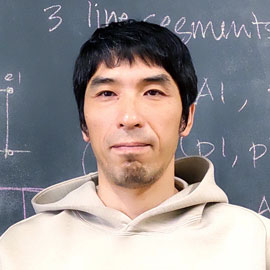
京都工芸繊維大学 工芸科学部 デザイン科学域 デザイン・建築学課程 准教授 松本 裕司 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
工芸科学、デザイン科学先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標8]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-8-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )
